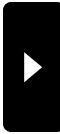2022年09月02日
久しぶりの北アルプスは雨
予定していた北アルプス遠征。
週間天気予報ではずっと雨予報。
7月も中止になったし、なんか今年はツイてないな・・・
予報も改善しないことから、北アルプスは諦めて別の行き先を考えることに。
日本全国雨模様なので、雨でも楽しめるところ・・・。
黒部の下ノ廊下でも良いかと思ったものの、開通期間外で×。
ロングトレイルの熊野古道 小辺路や、美ヶ原の中央分水嶺トレイルを提案するもいくみん乗り気なし。
出来れば北アルプスに行きたいらしい。
そりゃ自分も北アルプス行きたいけど、この天候じゃな・・・と思ってたところに台風11号発生。
気圧配置が変わって、初日は雨予報から晴れ予報に。(翌日は×)
おお、これなら初日だけなら楽しめるかも・・・。
それならダメもとで、予報を信じていきましょうか。
行き先は日本のマッターホルン、槍ヶ岳。
いくみんとの北アルプスは4回目。(1回目、2回目、3回目) 続きを読む
週間天気予報ではずっと雨予報。
7月も中止になったし、なんか今年はツイてないな・・・
予報も改善しないことから、北アルプスは諦めて別の行き先を考えることに。
日本全国雨模様なので、雨でも楽しめるところ・・・。
黒部の下ノ廊下でも良いかと思ったものの、開通期間外で×。
ロングトレイルの熊野古道 小辺路や、美ヶ原の中央分水嶺トレイルを提案するもいくみん乗り気なし。
出来れば北アルプスに行きたいらしい。
そりゃ自分も北アルプス行きたいけど、この天候じゃな・・・と思ってたところに台風11号発生。
気圧配置が変わって、初日は雨予報から晴れ予報に。(翌日は×)
おお、これなら初日だけなら楽しめるかも・・・。
それならダメもとで、予報を信じていきましょうか。
行き先は日本のマッターホルン、槍ヶ岳。
いくみんとの北アルプスは4回目。(1回目、2回目、3回目) 続きを読む
2014年08月17日
北鎌尾根 単独 暴風雨 考察
北鎌尾根に関する個人的な考察の記録。
北鎌尾根へのルート
1日目はこちら
2日目はこちら
個人的な感覚になるが、北鎌尾根の難易度は高い。
今回のルートは 上高地→槍沢→大曲→水俣乗越→北鎌沢出会→北鎌沢右俣→北鎌のコル→槍ヶ岳→飛騨乗越→槍平小屋→新穂高温泉 の1泊2日。
条件は単独、強風、雨、登攀道具無し。
■難易度
ある書籍では奥穂~西穂の縦走ルートと同じ【登攀1級上】と同じ扱いであるが、雨が降っていた事もあり、北鎌尾根は数段上と感じた。比べたらいけないくらい上。
雨が降っていなかったとしても上。
ネット上では難しくないような書き方をしている記事も見かけるが、安易に信じないようにした方が良いです。
そういう人達は実力が伴ってる人なんでしょうが、遭難者増加の助長をしてるかも知れません。
安易に行けば事故を起こす可能性が非常に高い場所です。
個人的には「是非行ってみて!」なんて絶対言える様な場所ではありません。
奥穂~西穂縦走では「体力があれば行ける」と書いたが、北鎌尾根は体力だけじゃ行けない。
(過去、ジャンダルムの記録へ)
体力は絶対。あとクライミングの技術、そしてパワーも備えていないと厳しいという実感。
普段からトレーニングしている人しか行かない方が賢明。
ここに来る様な人であれば当然備わってると思うが、地図を読む力と岩歩きの経験は必須。
単独ではなおさら。
単独とパーティーでは安心感が全然違うと思われる。確保もしてもらえる。
是非パーティーで行く事を推奨。
自分自身に関しても悪天候に行くんであればもっと実力を付けないとダメ。
今回は運が良かった。
■天気
当然晴れの日を目指して行くべき。
今回、行きたくて雨の中北鎌尾根に行った訳じゃない。
日曜日時点での天気予報が外れ、それを信じた自分が悪いだけ。
予想天気図からピーカンとはならないなぁ・・・というくらいしか考えられなかった。
今回は台風が直前で通過しただけあって天上沢、北鎌沢の水量が事前情報と全然違った。
北鎌沢の登りも厳しくなるし、当然北鎌尾根上はさらに危険度が増す。
これに尾根上では強風がプラスされるので、夏山なのに予想外の寒さに今回はまいった。
尾根に出てしまえば5時間ほどは逃げ道なし。
今回はまさにこれで、1日目に尾根上に出てしまったので、翌日は『行くも地獄、帰るも地獄』という状態。
まぁ尾根上に行くと決めた時点で、先に進む事を決心してはいたんだけども。
水量の増した北鎌沢を下る危険性と、水俣乗越へ登り返すザレザレのルートを思い返すだけで、今回はほぼ迷わず 北鎌尾根に進む事を選択した次第。決して撤退を考えていなかった訳ではない。どちらも地獄だっただけ。
天気が悪ければ北鎌沢出会までで、早めの判断を。
(出来れば水俣乗越までで。荒天時に天上沢の遡上は沢が多くて迷うかも)
■日程&ルート
北鎌尾根へ行くルートは主に3つ
1、今回の、上高地(もしくは新穂高側)から水俣乗越を天上沢へ下るルート
2、大天井ヒュッテから貧乏沢を下り北鎌沢出会を目指すルート
3、高瀬ダムから入り水俣川を遡上するクラシックルート
今回のルートに関しては、2500mほどまで水俣乗越へ登り、1800mほどの北鎌沢出会までの下り。
さらに2500mほどの北鎌のコルまで登り返すという事を1日でこなしたが、体力的に結構きつい。
出来れば北鎌沢出会で幕営すべきかもしれない。そうすると2泊3日の行程になるが、北鎌尾根なのでそれくらいの余裕は必要なのかもしれない。急いでも危険が増すだけ。尾根上を歩いてる人にも迷惑が掛かるだろうし。
安全に北鎌尾根を踏破するために荷物を軽量化したいのであれば、大天井ヒュッテの小屋泊まりとし、テン泊装備無しとなる貧乏沢経由のルートが良いかもしれない。うん、これが一番安全性高いかも。
ただ時間は掛かるかもしれないが、高度を少しづつ上げていける天上沢を遡上していき、行こうと思えばP1から取 り付けるクラシックルートが実は一番楽しめるコースなのかも知れない。
■装備
ヘルメットは必須。
今回はハーネス・ザイル等の登攀道具については単独なので持ち込まなかった。
どちらかというと、日数制限もあり荷物を軽くしたかったというのが本音。
事前情報でも登攀道具は無しでも可、とあったためだが、パーティー組むなら絶対あった方が良い。
そして荷物はなるべく軽くし、小さくパッキングする。
体力の消耗も激しいルートなので、荷物でバランス崩して滑落は十分にありえる。
靴については個人差もあるが、夏季に限ればアプローチシューズ的なものが良い。
テン泊装備で行くのであれば、テントの軽量化をはかりツェルトで済ませる事も良いかもしれない。
ツェルト、持ってないので尾根上の強風に耐えられるかどうかは不明ですが・・・
あとGPSがあれば心強い。今回は頼みのiPhone GPSが雨で死んでしまってピンチに。
高いけどガーミンとか買えればいいんだけどね、無理だね。。。
iPhoneの雨&結露対策。気を付けてはいたんだけど必要と分かった。。。
■事前情報
この時代、情報はいくらでも手に入る。
ただ今回に関してはあまり詰め込むような事はしなかった。
あまりにも情報を入れて北鎌尾根を踏破してもなぁ・・・せっかくだから自分の実力で行きたいよなぁ・・・なんていう自己満 足を満たしたかったからだが、だから道迷いも結構あった。特に北鎌沢右俣遡上で。
あと北鎌沢出会では、ここで本当にいいのか?という不安が強かった。
結果として自信には繋がったがお勧めできない。素直にポイントとなる事前情報を頂きましょう。
ただし北鎌尾根に関する情報は案内看板も何も無いので、書いてる人によって違うこともありました。
その辺は気を付けないといけないところです。
■保険と登山届
山岳保険には必ず入りましょう。
上高地での登山届はもうすぐ義務化されるようです。
実は私、山岳保険に先月はいったばかりです・・・
■個人的な忘備録
iPhoneの雨対策、というか結露の対策が何か必要。
高度が大きく変化(温度変化)が激しい場所ではケースに入れない方が逆に良いかもしれない。
トレッキングポールの収納場所を考える必要がある。
両手を使いたい時、ザックを降ろさなくても、すぐにポールを仮にしまえる方法。
安全面に大きく貢献するはず。
今回カメラは軽量化の点から一眼は止め、昔のデジカメ Canon S90 を持参した。
結果、山行の記録は出来たが、一眼に慣れてしまった眼にこの写りはストレス大。
今後のバリエーションルートの事も考えると、写りの良いコンパクトなカメラが欲しい。。。
今回初めて導入した装備にハイドレーションがあるが、とっても使える。
北鎌尾根などの休憩ポイントもロクにないような場所では、その貢献度は大きい。
ツェルトはもしもの為にも購入しておいた方がいい装備。
今回のような場所ではテント代わりにツェルト装備にしたら大幅な軽量化が可能。
お金に余裕があればなあ。。。
登山靴は山行スタイルに合わせて変化させた方がいい。
重登山靴でバリエーションルートはやや厳しいかもしれない。
■北鎌尾根を目指した目的
北鎌尾根を目指した理由は有名なバリエーションルートであったから。
有名な場所は他にもあるけど、単独で行けるここはやはり魅力的で。
自分は基本ソロなんで。
最近、どの山を歩いていても多少の物足りなさがあって、ただ歩いてる感が否めなく。
・・・これは完全に個人の考え方ですが。
難しいといわれる場所の経験は奥穂~西穂間ですが、思い返すとあれは楽しかった。
岩稜登りが特に楽しかった。剣、早月尾根の岩稜も前穂の登りも楽しかった。
そんな事を考えてると、一般登山道最難関といわれている奥穂~西穂間以上のルート?
もうバリエーションの世界だなぁ、となりました。
自分自身に対する挑戦でもあります。自分はまだ頑張れる!
そしてもう一つの理由。
子供達が大きくなって親になって、自分の息子達に「うちの親父は昔一人でこんな所に行ったらしい、ほんまバカやろ?いくみんもよー許すよなぁ。」と、笑って昔話をしてもらえる様な親父になりたい。
子供達が親父を自慢できるような事を何か残したい、といつも思ってる。
でも死んだら意味ない。そこは気を付けないと。
これからまだまだ頑張ります。
北鎌尾根へのルート
1日目はこちら
2日目はこちら
個人的な感覚になるが、北鎌尾根の難易度は高い。
今回のルートは 上高地→槍沢→大曲→水俣乗越→北鎌沢出会→北鎌沢右俣→北鎌のコル→槍ヶ岳→飛騨乗越→槍平小屋→新穂高温泉 の1泊2日。
条件は単独、強風、雨、登攀道具無し。
■難易度
ある書籍では奥穂~西穂の縦走ルートと同じ【登攀1級上】と同じ扱いであるが、雨が降っていた事もあり、北鎌尾根は数段上と感じた。比べたらいけないくらい上。
雨が降っていなかったとしても上。
ネット上では難しくないような書き方をしている記事も見かけるが、安易に信じないようにした方が良いです。
そういう人達は実力が伴ってる人なんでしょうが、遭難者増加の助長をしてるかも知れません。
安易に行けば事故を起こす可能性が非常に高い場所です。
個人的には「是非行ってみて!」なんて絶対言える様な場所ではありません。
奥穂~西穂縦走では「体力があれば行ける」と書いたが、北鎌尾根は体力だけじゃ行けない。
(過去、ジャンダルムの記録へ)
体力は絶対。あとクライミングの技術、そしてパワーも備えていないと厳しいという実感。
普段からトレーニングしている人しか行かない方が賢明。
ここに来る様な人であれば当然備わってると思うが、地図を読む力と岩歩きの経験は必須。
単独ではなおさら。
単独とパーティーでは安心感が全然違うと思われる。確保もしてもらえる。
是非パーティーで行く事を推奨。
自分自身に関しても悪天候に行くんであればもっと実力を付けないとダメ。
今回は運が良かった。
■天気
当然晴れの日を目指して行くべき。
今回、行きたくて雨の中北鎌尾根に行った訳じゃない。
日曜日時点での天気予報が外れ、それを信じた自分が悪いだけ。
予想天気図からピーカンとはならないなぁ・・・というくらいしか考えられなかった。
今回は台風が直前で通過しただけあって天上沢、北鎌沢の水量が事前情報と全然違った。
北鎌沢の登りも厳しくなるし、当然北鎌尾根上はさらに危険度が増す。
これに尾根上では強風がプラスされるので、夏山なのに予想外の寒さに今回はまいった。
尾根に出てしまえば5時間ほどは逃げ道なし。
今回はまさにこれで、1日目に尾根上に出てしまったので、翌日は『行くも地獄、帰るも地獄』という状態。
まぁ尾根上に行くと決めた時点で、先に進む事を決心してはいたんだけども。
水量の増した北鎌沢を下る危険性と、水俣乗越へ登り返すザレザレのルートを思い返すだけで、今回はほぼ迷わず 北鎌尾根に進む事を選択した次第。決して撤退を考えていなかった訳ではない。どちらも地獄だっただけ。
天気が悪ければ北鎌沢出会までで、早めの判断を。
(出来れば水俣乗越までで。荒天時に天上沢の遡上は沢が多くて迷うかも)
■日程&ルート
北鎌尾根へ行くルートは主に3つ
1、今回の、上高地(もしくは新穂高側)から水俣乗越を天上沢へ下るルート
2、大天井ヒュッテから貧乏沢を下り北鎌沢出会を目指すルート
3、高瀬ダムから入り水俣川を遡上するクラシックルート
今回のルートに関しては、2500mほどまで水俣乗越へ登り、1800mほどの北鎌沢出会までの下り。
さらに2500mほどの北鎌のコルまで登り返すという事を1日でこなしたが、体力的に結構きつい。
出来れば北鎌沢出会で幕営すべきかもしれない。そうすると2泊3日の行程になるが、北鎌尾根なのでそれくらいの余裕は必要なのかもしれない。急いでも危険が増すだけ。尾根上を歩いてる人にも迷惑が掛かるだろうし。
安全に北鎌尾根を踏破するために荷物を軽量化したいのであれば、大天井ヒュッテの小屋泊まりとし、テン泊装備無しとなる貧乏沢経由のルートが良いかもしれない。うん、これが一番安全性高いかも。
ただ時間は掛かるかもしれないが、高度を少しづつ上げていける天上沢を遡上していき、行こうと思えばP1から取 り付けるクラシックルートが実は一番楽しめるコースなのかも知れない。
■装備
ヘルメットは必須。
今回はハーネス・ザイル等の登攀道具については単独なので持ち込まなかった。
どちらかというと、日数制限もあり荷物を軽くしたかったというのが本音。
事前情報でも登攀道具は無しでも可、とあったためだが、パーティー組むなら絶対あった方が良い。
そして荷物はなるべく軽くし、小さくパッキングする。
体力の消耗も激しいルートなので、荷物でバランス崩して滑落は十分にありえる。
靴については個人差もあるが、夏季に限ればアプローチシューズ的なものが良い。
テン泊装備で行くのであれば、テントの軽量化をはかりツェルトで済ませる事も良いかもしれない。
ツェルト、持ってないので尾根上の強風に耐えられるかどうかは不明ですが・・・
あとGPSがあれば心強い。今回は頼みのiPhone GPSが雨で死んでしまってピンチに。
高いけどガーミンとか買えればいいんだけどね、無理だね。。。
iPhoneの雨&結露対策。気を付けてはいたんだけど必要と分かった。。。
■事前情報
この時代、情報はいくらでも手に入る。
ただ今回に関してはあまり詰め込むような事はしなかった。
あまりにも情報を入れて北鎌尾根を踏破してもなぁ・・・せっかくだから自分の実力で行きたいよなぁ・・・なんていう自己満 足を満たしたかったからだが、だから道迷いも結構あった。特に北鎌沢右俣遡上で。
あと北鎌沢出会では、ここで本当にいいのか?という不安が強かった。
結果として自信には繋がったがお勧めできない。素直にポイントとなる事前情報を頂きましょう。
ただし北鎌尾根に関する情報は案内看板も何も無いので、書いてる人によって違うこともありました。
その辺は気を付けないといけないところです。
■保険と登山届
山岳保険には必ず入りましょう。
上高地での登山届はもうすぐ義務化されるようです。
実は私、山岳保険に先月はいったばかりです・・・
■個人的な忘備録
iPhoneの雨対策、というか結露の対策が何か必要。
高度が大きく変化(温度変化)が激しい場所ではケースに入れない方が逆に良いかもしれない。
トレッキングポールの収納場所を考える必要がある。
両手を使いたい時、ザックを降ろさなくても、すぐにポールを仮にしまえる方法。
安全面に大きく貢献するはず。
今回カメラは軽量化の点から一眼は止め、昔のデジカメ Canon S90 を持参した。
結果、山行の記録は出来たが、一眼に慣れてしまった眼にこの写りはストレス大。
今後のバリエーションルートの事も考えると、写りの良いコンパクトなカメラが欲しい。。。
今回初めて導入した装備にハイドレーションがあるが、とっても使える。
北鎌尾根などの休憩ポイントもロクにないような場所では、その貢献度は大きい。
ツェルトはもしもの為にも購入しておいた方がいい装備。
今回のような場所ではテント代わりにツェルト装備にしたら大幅な軽量化が可能。
お金に余裕があればなあ。。。
登山靴は山行スタイルに合わせて変化させた方がいい。
重登山靴でバリエーションルートはやや厳しいかもしれない。
■北鎌尾根を目指した目的
北鎌尾根を目指した理由は有名なバリエーションルートであったから。
有名な場所は他にもあるけど、単独で行けるここはやはり魅力的で。
自分は基本ソロなんで。
最近、どの山を歩いていても多少の物足りなさがあって、ただ歩いてる感が否めなく。
・・・これは完全に個人の考え方ですが。
難しいといわれる場所の経験は奥穂~西穂間ですが、思い返すとあれは楽しかった。
岩稜登りが特に楽しかった。剣、早月尾根の岩稜も前穂の登りも楽しかった。
そんな事を考えてると、一般登山道最難関といわれている奥穂~西穂間以上のルート?
もうバリエーションの世界だなぁ、となりました。
自分自身に対する挑戦でもあります。自分はまだ頑張れる!
そしてもう一つの理由。
子供達が大きくなって親になって、自分の息子達に「うちの親父は昔一人でこんな所に行ったらしい、ほんまバカやろ?いくみんもよー許すよなぁ。」と、笑って昔話をしてもらえる様な親父になりたい。
子供達が親父を自慢できるような事を何か残したい、といつも思ってる。
でも死んだら意味ない。そこは気を付けないと。
これからまだまだ頑張ります。
2014年08月16日
北鎌尾根 単独 暴風雨 2日目
1日目はこちら
北鎌尾根へのルート
■8月12日(火)
強風がテントをたたき、とても熟睡は出来ず、やや湿った状態のダウンジャケットでジメッとした寝起き。
うつらうつらとしながらも、夜中に何度もテントの空気口から外を覗くが真っ白な霧の中。
雨は幸い降ってないようなので、今に霧も晴れるだろう、いや、晴れてもらわねば困る。
今日はいよいよ本格的な北鎌の核心部に突入するんだから。。。
雨の中の北鎌は避けたい。
昨日の沢登りでも何度もすべり、とにかく足場とホールドする手元が不安定で怖い。
これまで履き慣れてきたゴローのダックライトからザンバラン ヴィオーズ・プラス GTに替えた関係もあり、思った以上にフリクションが 効かない。
テント泊装備なので重登山靴のヴィオーズ・プラス GTにしたが、岩稜歩きでは圧倒的に軽登山靴のダックライトの方が信頼で きる。いや、その時はアプローチシューズやクライミングシューズが欲しいと思いながら歩いてた。
ダックライトを履いてくれば良かったな・・・と思うものの、台風直後のあの北鎌沢の水量ではダックライトが耐えら れたかどうかは怪しかった。結局最後まで足元の濡れは皆無で、その点は重登山靴の信頼度は高い。
05:10 P8ピーク出発
強風にあおられながらも何とかテントを撤収、朝飯代わりのチョコバーを食し、P8の先にある天狗の腰掛と独標に 向かってクライミング開始。
当然ながらこの先には水場がないので、残り少ない貴重な水を朝食でガブガブ飲む訳にはいかなかった。
出発した途端に・・・あれ?雨ですか・・・?
・・・くっそー!
と思うものの、自然には逆らえないので再びザックを降ろしレインウェアを着込む。
さぁ、再出発!と歩いた途端に・・・え・・・あれ?雨止みましたか???
普段ならこのまましばらく歩くものの、ここは北鎌。
出来るだけ動きやすい服装にしたい。またザックを降ろしレインウェアを仕舞う。
歩く・・・数分後に本降り・・・
・・・くそー!!!
結局そのままこの日はレインウェアを着続ける事になる。
たった数分のタイムロスが惜しい、と言うか面倒くさい。。。
天狗の腰掛を抜け、独標の下、千丈沢側にあるトラバースラインに入る。

そのまま横移動するのではなく、一旦稜線側に出てからトラバース開始。
さすがに難路。気を抜けば死ねる箇所の連続。慎重に進んでいく。

トラバースラインの途中で、独標への稜線に向け直登開始。
独標下のチムニーと呼ばれるポイントも抜けたが、事前情報では難しくないとあった。
結果して行けたものの、決して容易な場所ではないというのが実感。
雨でとにかくホールドする手と重登山靴が滑る。
背が低くパワーのない女性などには難しい場所だろうなぁ、など思いながら通過した。
事前に調べていた通り、北鎌尾根は踏み跡が無数に付いており、何も考えずに踏み跡に沿って歩くと知らない間に 歩行困難な場所に迷い込む。コースなんてここには無い。自分で見て考えて進む。
迷ったら稜線通しに、とも聞くが、何度も懸垂下降ポイントにたどり着いて難儀した。
単独行なので今回はハーネス・ザイルの類は持ち込んでなく、懸垂下降ポイントを何度か慎重に下った。
稜線は当然ながら風がきつく、落ちたら100mは滑落という場所が多く出現するので、ケースバイケースでトラバー スラインを選択することも必要なことだろう。
P14くらいまで進んだ頃だろうか?
なんせ辺りはガスガスで暴風雨。
視界は10mほどが常であり、先がぜんぜん見えない。
当然槍ヶ岳なんてまだ一度も見ていない。見れる気配もない。
時折ガスが切れる合間に硫黄尾根などの場所を確認し、方角の感覚を修正していく。
トラバースラインの踏み跡に頼って下れば、ガスで稜線が見えなくなってそのまま変な場所に下って行きそうで不 安になる。戻れる時に稜線に戻ろうと決めて歩みを進めた。
稜線に向かう途中、何てことはないけど嫌な岩に出くわした。
3mほどの大きさで、稜線に向かい30度ほどの傾斜で5cmほど足の置き場になりそうなエッジが続いてる岩。
岩の角度的に3点支持ができず、2足歩行になるシチュエーション。
これまでの道のりで散々滑って怖い思いをしてきたので、嫌だなぁ・・・と思いながら慎重にその5cmのエッジに左足 を乗せ、右足を乗せた瞬間、落下。
一瞬の出来事で、足が滑ったのか、支えようとした左手が滑ったのかは分からないが、気付いた時には右目前に岩 。
手で支える間もない一瞬の出来事。
ザックを含めた全体重が右側頭部から岩に突っ込んだ。
ヘルメットを通してもクラッとする衝撃だったが、なんとか気は失わないで済み1mほど下の岩に立てたものの、そ の下は50mほど千丈沢側に切れ落ちてる場所で、今回の山行で一番ヒヤッとした場面。
助かったのは間違いなくヘルメットのおかげで、落石から身を護るために買ったヘルメットだけどこんな形で役立 ってくれた。
ヘルメットをしてなければ間違いなく気を失うほどの衝撃で、そのまま50m以上落ちて死んで、単独だし、天気は悪 いし、しばらく見つからなかっただろうな・・・と思う。
ヘルメットに感謝。
大事に使うし、これから危ない所では必ずしよう。
そんな出来事に心も折れかけた頃、あら?
・・・もしかして槍ですかあれは???
ガスの切れ間から何となく見えてきた槍らしき影。
少し元気でた!

(両日とも天気が悪くて写真はほとんど撮ってない)
08:50 北鎌平
これまで稜線通しを基本としてきたこともあり暴風雨に晒されて体も冷え切り、それでも目標地点がぜんぜん見え なく心が折れそうになったが、槍が見えたことでようやく活力が生まれる。
さぁもうひとふん張りでここを抜けられるぞ・・・
槍の直下に立つと、デカイ。
そしてこれまでとは見上げる角度がぜんぜん違う。
真上を向かないとルートが確認できないが、上を向くとヘルメットがザックにあたってズレ、視界がなくなる。
それくらい見上げないといけないほど槍は垂直の岩壁。
ここ、今の自分に登れるんかいな?
相変わらず暴風雨は止まず、滑る怖さに加えてこの辺りでさらに悪い出来事が手の冷え。
4時間近く雨風に晒された指が冷たくて痺れだしていて、うまく動かせない。
「うわ~やばいわ~」と独り言で声に出していった言葉も、寒さで口が動かずうまく喋れない事に気付く。
そんな状況の自分が、そんな岩壁見あげてる姿にニガ笑い。
たぶん雨風がなければ難易度はぜんぜん違うんだろう。
フリクションが効けば、指の感覚がちゃんとあれば行けるんだろう。
でも今の自分はそれに自信が持てない。
待ってても寒くなる一方で、身を隠す場所もない。
指の感覚が回復する可能性はない。
これ以上悪くなる前に早く進もう、と意を決する。
この時点では、ここまでほぼずっと千丈沢側(北西)からの風が吹き続き、雲の厚さからも天気が回復する期待はなく、たぶん台風11号(この時点で温帯低気圧)の進みが遅く、自分のほぼ真北からやや東側にあって、思ったより前線が離れてないのかもしれないなぁ、待つよりは早めに行程を終わらせた方がいいだろうな、と思っていた。
急ぎながらも慎重に、ルートファインディングを誤らないように進んでいく。
ところどころに残置ハーケンや古いザイル。
みんないろんな所からトライしているみたい。
自分は自分自身の状況からいける道を探し選択し、高度を少しづつ上げていく。
写真ではわからないけど、ほぼ垂直に近いような岩稜が連続する。
とにかく濡れた岩が嫌。

そして最後の核心部はやはりチムニー。
高さ5mほどのチムニー。
これ今の自分には厳しいな・・・
絶対に滑る、まず指に力入らん・・・とネガティブな事ばかり考える。
暴風雨に晒され続けてると良い方向には思考が向かない。冬山でよく経験する感覚。
一旦あきらめ他のルートを探すものの、無し。
その間にもどんどん体温が奪われていく。
迷ってる時間はない。
結局自分にはここが一番可能性のある場所と判断し選択した。
40cmほどの割れ目のチムニーだが、当然ザックを担いだ体が入る訳もなく、右壁の手がかり足がかりを探して重い 体を持ち上げる。
1mほど体を上げる場所はすぐに見つかったが、そこからが見つからない。
あるにはあるが、この程度の引っ掛かりでは今の自分の指に体重をかけられる信頼度はなく、すっぽ抜けそ うだなぁ・・・右手に左手添えて2点で登るか?いや、そんな危険は冒さない方が良いだろう・・・と手探りで他の手がか りを探す。
スマートさに拘らなければ背中のザックを壁に押し付けて登れば良かったかもしれないが、こんな時でもA型の気質 か、それは本能的に嫌がる。自身の意図しない動きになるのが嫌なのかもしれないなぁ。
手がかりを探ってると、右手側にここなら大丈夫かな?というポイントを見つけて、慎重に確認。
多少体のバランスは悪くなるが、それは筋力でカバー出来るはず!
大丈夫か?本当に大丈夫か?
大丈夫!
よし、行くぞ!
チムニーを抜けた後、左手側に白い杭。
どこかで見たことある風景。事前情報で確認した写真の風景。
その杭に近付き天上沢側を見上げると、おお、ここ登れそうだなというポイント。
慎重にそのポイントを登っていき、人ひとりが立てる場所で一休み。
ガスでほとんど先が見えていないので、近付いているのは確かだけど、頂上まで後どれくらいか・・・
そんな事を考えながら上を見上げると、そこに茶色い社が見えた。
槍ヶ岳頂上の社だ。
着いた!
09:20 槍ヶ岳頂上
暴風雨の槍ヶ岳頂上には誰も居らず頂上を独り占め、ってそんな良いものではない。
早くこの場から立ち去りたい。暴風雨をしのげる安全な一般登山道に戻りたい。
暴風雨の中、無理やり2枚だけ写真を撮り、すぐに下山を開始した。
槍ヶ岳頂上での滞在時間は20秒ほどだった。

09:35 槍ヶ岳山荘
しっかり固定された鉄製の梯子やチェーンを下って槍の肩にある槍ヶ岳山荘に到着。
山荘に入ってゆっくり温かいものでも・・・と考えたが、山荘の中には凄い人が見える。
でも前日の大曲からまったく人に遭遇していなかったので、久しぶりにホッとする。
この雨風でみんな行動を控え、小屋の中から外の様子を伺っていた。
とてもびしょびしょの自分が入っていける様なスペースは無い。
結局休憩も取らず槍ヶ岳山荘を後にする。
8月9日から始まっているTJAR2014(トランスシ゛ャハ゜ンアルフ゜スレース)でも素通りして行ったんだろうなぁ。
(そういえば昨日は横尾かどこかのテン場でTJARの緑色のテントを見かけた。スタッフのかな?)
09:40 下山
飛騨側に下りるか?槍平方面に戻るか?
少し考えたが同じルートは通りたくなく、飛騨乗越を経由して新穂高ロープウェイまで下りる事に決めた。
今考えれば西鎌尾根経由で行けばよかったな、とちょっと後悔。
飛騨乗越は昔ジャンダルムに行った時に通った道。
懐かしさはあるが、一度も歩いてない西鎌尾根を少しでも歩ければ良かったな。
11:20 槍平小屋
急いだ割にはコースタイムより遅いくらいで到着。
山と渓谷地図のコースタイムあってる!?(時間とり間違えたんやろか?)
下り道は登山道が雨で沢のように水が流れ、今回は沢登りも沢下りも楽しめた山行だったなぁ、と思いながら下る 。一般登山道の安心感から余裕が生まれたが、それが最後の怪我に繋がる・・・。
普通の登山道、岩と岩をまたいで進んでいた時、右足が滑ってバランスを崩す。
とっさに右手のポールで支えようとするが、そのポールがまた滑る。
右わき腹から岩に落下。
数日たった今でも、何する時でも右わき腹が痛い。ヒビくらい入ったかな???
気を抜き過ぎた罰。普通の登山道で情けない、、、と思いながら下山。
山は最後まで、家に帰るまで、気は抜き過ぎないこと。
13:40 新穂高ロープウェイ
下りの途中からは新穂高ロープウェイバスの出発時間を考えながらの下山。
13:46のバスを逃がすと1時間待たないといけない。
間に合わすように急ぐが、何せ2日間酷使してきた体、全身が痛くスピードあげれない。
残り10分、もう少しなのに歩いてたんじゃ間に合わない。
最後はトレイルランナーのように走り出して間に合わせた。
ほぼ全ての行程がここで終わりだった。
15:00 アカンダナ駐車場着
19:00 自宅着
下山後、いくみんに連絡を取ろうにも雨でiPhoneが死亡しており連絡出来ないまま車中の人に。
公衆電話を探しながら帰ったが、最近は公衆電話ないね。
結局下山後2時間してから公衆電話を見つけたが、ちょっと心配掛けたかな。
今回は雨で色々な事を教わった。
北鎌尾根の事も含め、次回の記事に残す。
北鎌尾根へのルート
■8月12日(火)
強風がテントをたたき、とても熟睡は出来ず、やや湿った状態のダウンジャケットでジメッとした寝起き。
うつらうつらとしながらも、夜中に何度もテントの空気口から外を覗くが真っ白な霧の中。
雨は幸い降ってないようなので、今に霧も晴れるだろう、いや、晴れてもらわねば困る。
今日はいよいよ本格的な北鎌の核心部に突入するんだから。。。
雨の中の北鎌は避けたい。
昨日の沢登りでも何度もすべり、とにかく足場とホールドする手元が不安定で怖い。
これまで履き慣れてきたゴローのダックライトからザンバラン ヴィオーズ・プラス GTに替えた関係もあり、思った以上にフリクションが 効かない。
テント泊装備なので重登山靴のヴィオーズ・プラス GTにしたが、岩稜歩きでは圧倒的に軽登山靴のダックライトの方が信頼で きる。いや、その時はアプローチシューズやクライミングシューズが欲しいと思いながら歩いてた。
ダックライトを履いてくれば良かったな・・・と思うものの、台風直後のあの北鎌沢の水量ではダックライトが耐えら れたかどうかは怪しかった。結局最後まで足元の濡れは皆無で、その点は重登山靴の信頼度は高い。
05:10 P8ピーク出発
強風にあおられながらも何とかテントを撤収、朝飯代わりのチョコバーを食し、P8の先にある天狗の腰掛と独標に 向かってクライミング開始。
当然ながらこの先には水場がないので、残り少ない貴重な水を朝食でガブガブ飲む訳にはいかなかった。
出発した途端に・・・あれ?雨ですか・・・?
・・・くっそー!
と思うものの、自然には逆らえないので再びザックを降ろしレインウェアを着込む。
さぁ、再出発!と歩いた途端に・・・え・・・あれ?雨止みましたか???
普段ならこのまましばらく歩くものの、ここは北鎌。
出来るだけ動きやすい服装にしたい。またザックを降ろしレインウェアを仕舞う。
歩く・・・数分後に本降り・・・
・・・くそー!!!
結局そのままこの日はレインウェアを着続ける事になる。
たった数分のタイムロスが惜しい、と言うか面倒くさい。。。
天狗の腰掛を抜け、独標の下、千丈沢側にあるトラバースラインに入る。
そのまま横移動するのではなく、一旦稜線側に出てからトラバース開始。
さすがに難路。気を抜けば死ねる箇所の連続。慎重に進んでいく。
トラバースラインの途中で、独標への稜線に向け直登開始。
独標下のチムニーと呼ばれるポイントも抜けたが、事前情報では難しくないとあった。
結果して行けたものの、決して容易な場所ではないというのが実感。
雨でとにかくホールドする手と重登山靴が滑る。
背が低くパワーのない女性などには難しい場所だろうなぁ、など思いながら通過した。
事前に調べていた通り、北鎌尾根は踏み跡が無数に付いており、何も考えずに踏み跡に沿って歩くと知らない間に 歩行困難な場所に迷い込む。コースなんてここには無い。自分で見て考えて進む。
迷ったら稜線通しに、とも聞くが、何度も懸垂下降ポイントにたどり着いて難儀した。
単独行なので今回はハーネス・ザイルの類は持ち込んでなく、懸垂下降ポイントを何度か慎重に下った。
稜線は当然ながら風がきつく、落ちたら100mは滑落という場所が多く出現するので、ケースバイケースでトラバー スラインを選択することも必要なことだろう。
P14くらいまで進んだ頃だろうか?
なんせ辺りはガスガスで暴風雨。
視界は10mほどが常であり、先がぜんぜん見えない。
当然槍ヶ岳なんてまだ一度も見ていない。見れる気配もない。
時折ガスが切れる合間に硫黄尾根などの場所を確認し、方角の感覚を修正していく。
トラバースラインの踏み跡に頼って下れば、ガスで稜線が見えなくなってそのまま変な場所に下って行きそうで不 安になる。戻れる時に稜線に戻ろうと決めて歩みを進めた。
稜線に向かう途中、何てことはないけど嫌な岩に出くわした。
3mほどの大きさで、稜線に向かい30度ほどの傾斜で5cmほど足の置き場になりそうなエッジが続いてる岩。
岩の角度的に3点支持ができず、2足歩行になるシチュエーション。
これまでの道のりで散々滑って怖い思いをしてきたので、嫌だなぁ・・・と思いながら慎重にその5cmのエッジに左足 を乗せ、右足を乗せた瞬間、落下。
一瞬の出来事で、足が滑ったのか、支えようとした左手が滑ったのかは分からないが、気付いた時には右目前に岩 。
手で支える間もない一瞬の出来事。
ザックを含めた全体重が右側頭部から岩に突っ込んだ。
ヘルメットを通してもクラッとする衝撃だったが、なんとか気は失わないで済み1mほど下の岩に立てたものの、そ の下は50mほど千丈沢側に切れ落ちてる場所で、今回の山行で一番ヒヤッとした場面。
助かったのは間違いなくヘルメットのおかげで、落石から身を護るために買ったヘルメットだけどこんな形で役立 ってくれた。
ヘルメットをしてなければ間違いなく気を失うほどの衝撃で、そのまま50m以上落ちて死んで、単独だし、天気は悪 いし、しばらく見つからなかっただろうな・・・と思う。
ヘルメットに感謝。
大事に使うし、これから危ない所では必ずしよう。
そんな出来事に心も折れかけた頃、あら?
・・・もしかして槍ですかあれは???
ガスの切れ間から何となく見えてきた槍らしき影。
少し元気でた!
(両日とも天気が悪くて写真はほとんど撮ってない)
08:50 北鎌平
これまで稜線通しを基本としてきたこともあり暴風雨に晒されて体も冷え切り、それでも目標地点がぜんぜん見え なく心が折れそうになったが、槍が見えたことでようやく活力が生まれる。
さぁもうひとふん張りでここを抜けられるぞ・・・
槍の直下に立つと、デカイ。
そしてこれまでとは見上げる角度がぜんぜん違う。
真上を向かないとルートが確認できないが、上を向くとヘルメットがザックにあたってズレ、視界がなくなる。
それくらい見上げないといけないほど槍は垂直の岩壁。
ここ、今の自分に登れるんかいな?
相変わらず暴風雨は止まず、滑る怖さに加えてこの辺りでさらに悪い出来事が手の冷え。
4時間近く雨風に晒された指が冷たくて痺れだしていて、うまく動かせない。
「うわ~やばいわ~」と独り言で声に出していった言葉も、寒さで口が動かずうまく喋れない事に気付く。
そんな状況の自分が、そんな岩壁見あげてる姿にニガ笑い。
たぶん雨風がなければ難易度はぜんぜん違うんだろう。
フリクションが効けば、指の感覚がちゃんとあれば行けるんだろう。
でも今の自分はそれに自信が持てない。
待ってても寒くなる一方で、身を隠す場所もない。
指の感覚が回復する可能性はない。
これ以上悪くなる前に早く進もう、と意を決する。
この時点では、ここまでほぼずっと千丈沢側(北西)からの風が吹き続き、雲の厚さからも天気が回復する期待はなく、たぶん台風11号(この時点で温帯低気圧)の進みが遅く、自分のほぼ真北からやや東側にあって、思ったより前線が離れてないのかもしれないなぁ、待つよりは早めに行程を終わらせた方がいいだろうな、と思っていた。
急ぎながらも慎重に、ルートファインディングを誤らないように進んでいく。
ところどころに残置ハーケンや古いザイル。
みんないろんな所からトライしているみたい。
自分は自分自身の状況からいける道を探し選択し、高度を少しづつ上げていく。
写真ではわからないけど、ほぼ垂直に近いような岩稜が連続する。
とにかく濡れた岩が嫌。
そして最後の核心部はやはりチムニー。
高さ5mほどのチムニー。
これ今の自分には厳しいな・・・
絶対に滑る、まず指に力入らん・・・とネガティブな事ばかり考える。
暴風雨に晒され続けてると良い方向には思考が向かない。冬山でよく経験する感覚。
一旦あきらめ他のルートを探すものの、無し。
その間にもどんどん体温が奪われていく。
迷ってる時間はない。
結局自分にはここが一番可能性のある場所と判断し選択した。
40cmほどの割れ目のチムニーだが、当然ザックを担いだ体が入る訳もなく、右壁の手がかり足がかりを探して重い 体を持ち上げる。
1mほど体を上げる場所はすぐに見つかったが、そこからが見つからない。
あるにはあるが、この程度の引っ掛かりでは今の自分の指に体重をかけられる信頼度はなく、すっぽ抜けそ うだなぁ・・・右手に左手添えて2点で登るか?いや、そんな危険は冒さない方が良いだろう・・・と手探りで他の手がか りを探す。
スマートさに拘らなければ背中のザックを壁に押し付けて登れば良かったかもしれないが、こんな時でもA型の気質 か、それは本能的に嫌がる。自身の意図しない動きになるのが嫌なのかもしれないなぁ。
手がかりを探ってると、右手側にここなら大丈夫かな?というポイントを見つけて、慎重に確認。
多少体のバランスは悪くなるが、それは筋力でカバー出来るはず!
大丈夫か?本当に大丈夫か?
大丈夫!
よし、行くぞ!
チムニーを抜けた後、左手側に白い杭。
どこかで見たことある風景。事前情報で確認した写真の風景。
その杭に近付き天上沢側を見上げると、おお、ここ登れそうだなというポイント。
慎重にそのポイントを登っていき、人ひとりが立てる場所で一休み。
ガスでほとんど先が見えていないので、近付いているのは確かだけど、頂上まで後どれくらいか・・・
そんな事を考えながら上を見上げると、そこに茶色い社が見えた。
槍ヶ岳頂上の社だ。
着いた!
09:20 槍ヶ岳頂上
暴風雨の槍ヶ岳頂上には誰も居らず頂上を独り占め、ってそんな良いものではない。
早くこの場から立ち去りたい。暴風雨をしのげる安全な一般登山道に戻りたい。
暴風雨の中、無理やり2枚だけ写真を撮り、すぐに下山を開始した。
槍ヶ岳頂上での滞在時間は20秒ほどだった。
09:35 槍ヶ岳山荘
しっかり固定された鉄製の梯子やチェーンを下って槍の肩にある槍ヶ岳山荘に到着。
山荘に入ってゆっくり温かいものでも・・・と考えたが、山荘の中には凄い人が見える。
でも前日の大曲からまったく人に遭遇していなかったので、久しぶりにホッとする。
この雨風でみんな行動を控え、小屋の中から外の様子を伺っていた。
とてもびしょびしょの自分が入っていける様なスペースは無い。
結局休憩も取らず槍ヶ岳山荘を後にする。
8月9日から始まっているTJAR2014(トランスシ゛ャハ゜ンアルフ゜スレース)でも素通りして行ったんだろうなぁ。
(そういえば昨日は横尾かどこかのテン場でTJARの緑色のテントを見かけた。スタッフのかな?)
09:40 下山
飛騨側に下りるか?槍平方面に戻るか?
少し考えたが同じルートは通りたくなく、飛騨乗越を経由して新穂高ロープウェイまで下りる事に決めた。
今考えれば西鎌尾根経由で行けばよかったな、とちょっと後悔。
飛騨乗越は昔ジャンダルムに行った時に通った道。
懐かしさはあるが、一度も歩いてない西鎌尾根を少しでも歩ければ良かったな。
11:20 槍平小屋
急いだ割にはコースタイムより遅いくらいで到着。
山と渓谷地図のコースタイムあってる!?(時間とり間違えたんやろか?)
下り道は登山道が雨で沢のように水が流れ、今回は沢登りも沢下りも楽しめた山行だったなぁ、と思いながら下る 。一般登山道の安心感から余裕が生まれたが、それが最後の怪我に繋がる・・・。
普通の登山道、岩と岩をまたいで進んでいた時、右足が滑ってバランスを崩す。
とっさに右手のポールで支えようとするが、そのポールがまた滑る。
右わき腹から岩に落下。
数日たった今でも、何する時でも右わき腹が痛い。ヒビくらい入ったかな???
気を抜き過ぎた罰。普通の登山道で情けない、、、と思いながら下山。
山は最後まで、家に帰るまで、気は抜き過ぎないこと。
13:40 新穂高ロープウェイ
下りの途中からは新穂高ロープウェイバスの出発時間を考えながらの下山。
13:46のバスを逃がすと1時間待たないといけない。
間に合わすように急ぐが、何せ2日間酷使してきた体、全身が痛くスピードあげれない。
残り10分、もう少しなのに歩いてたんじゃ間に合わない。
最後はトレイルランナーのように走り出して間に合わせた。
ほぼ全ての行程がここで終わりだった。
15:00 アカンダナ駐車場着
19:00 自宅着
下山後、いくみんに連絡を取ろうにも雨でiPhoneが死亡しており連絡出来ないまま車中の人に。
公衆電話を探しながら帰ったが、最近は公衆電話ないね。
結局下山後2時間してから公衆電話を見つけたが、ちょっと心配掛けたかな。
今回は雨で色々な事を教わった。
北鎌尾根の事も含め、次回の記事に残す。
2014年08月13日
北鎌尾根 単独 暴風雨 1日目
暴風雨の中、北鎌尾根を単独。
気を抜けば死ねる場所だらけの北鎌尾根。
そして暴風雨でアクシデントが重なり危険な山行となりました。
北鎌尾根へのルート
■8月10日(日)
台風11号が通り過ぎた18時に自宅を出発し、アカンダナ駐車場に向かう。
でも岐阜県に入り豪雨にさらされる。あれなんかおかしいなぁ。
目的地は北アルプス、北鎌尾根からの槍ヶ岳。
一般登山道ではないバリエーションルート。
22時過ぎにアカンダナ駐車場付近に到着するが、03時にしか駐車場は開かず、平湯温泉の駐車場で仮眠。
半袖半ズボンで寝たら寒くて何度も起きるが、着込む気力なし。
何より軽トラのボディーを打つ雨音がやる気をそぐ。
■8月11日(月)
台風一過はどこへやら。
アカンダナ駐車場に04時に入場し、始発の04:50の上高地行バスを待っている時点で諦めてレインウェアを着込む。
雨は降り続く。
05:30 上高地出発
今回の山行の目的は北鎌尾根からの槍登頂。
槍ヶ岳が目的ではなく、あくまで目的は北鎌尾根。
しかも1泊2日の強行軍なので初日はとにかく距離を伸ばしたい。

08:40 槍沢ロッヂ
雨は降り続くどころか、ますます強雨に。
休憩もそこそこに先を急ぐ。
他の登山者も「台風一過だと思ったのになぁー」と話してる。
09:30 槍沢大曲
槍ヶ岳が目的ならこのまま真っ直ぐに殺生ヒュッテに向かうが、今回は大曲から水俣乗越を目指す。

10:30 水俣乗越
標高2500mほど。上高地から1000mほど高度を上げる。
ここまでが一般登山道。
ここからは登山道ではないバリエーションの世界。
全ては自己責任。

水俣乗越から登山道を外れ、北に進路をとり下る。
下り道はザレザレで、撤退の時にここを登り返すはキツイな・・・と思いながら下る。
途中には遭難者の物なのか、ずいぶん以前と思われる登山靴が片足だけ落ちてたり、ちょっと気味が悪い。
そんなところに雨が降る中、足を踏み入れていく自分も自分。
今回の山行は自分なりの挑戦。
途中雪渓も下り、標高をどんどん下げて1800m地点まで。
大きなアクシデントが1つ。
雨のせいか天候のせいかiPhoneのGPSが調子悪く感度が全然上がらない。(結局、我がiPhoneこの山行で息絶える・・・)
なにせ単独行が主の自分は、このGPSに助けてもらってる部分が多く、これがないと大幅な戦力ダウン。
バリエーションのルートに入っているので自分がどこを歩いてるのか、GPSが無いと方角と地図だけで判断しないといけなくなる。
なにせ登山道を歩いてるわけじゃないのだから。
上高地からずっと調子の悪かったiPhone GPSを頼むぞ!と祈るような気持ちで何度も見たが、回復する兆しなし。
それどころか表示される現在地がフラフラと彷徨っており、不安をさらにあおる。
もうこのGPSには頼れない。
こんな事もあろうかと事前に情報収集し、プリントアウトしていた紙を取り出す。
悲惨。
インクが汗と雨でにじんで何が何だかさっぱり分からない・・・

ぴーんち!
いや、冗談じゃなくピンチ。
大体、ここまで雨になるなんて思ってなかったもんなぁ…
もうこれで頼れるのは山岳地図だけ。
あとは自分の記憶にある知識。
12:00 北鎌沢出会
高度を1800mほどまで下げた場所に、今下ってきた主流の天上沢と北鎌沢が出会う北鎌沢出会がある。
といっても通常の登山道のような標識はないので、たぶんここがそうだな、と思うだけ。
予定してるルートはここから北鎌沢に進路を変更する。
山岳地図の等高線と、霧雨でかすんではいるが時折見える地形から判断した。
何せバリエーションのルートで、平日で、さらに天気が悪い条件なので、ひとっこひとり遭わない。
いれば聞けるのに、誰もいない。
台風の雨で増水してると思われる沢の轟音が聞こえるだけ。
とにかく不安。
ここで良いのか?
本当にここなのか?
大丈夫か自分!!
通常ならここの北鎌沢出会で幕営するんじゃなかろうか。
テント泊の装備を担いで上高地から歩いてきて12時。
ここが北鎌沢出会かどうかも怪しく、ここから先に進めば標高はまた2500mほどまで上げないといけない。
当然歩いたこともない北鎌沢。道迷いがひじょうに多いと言われている北鎌沢。
もう勝負勝負!
自分を信じろ!
北鎌沢出会を後にし、西に進路を変更、北鎌沢を遡上する。
1500mから2500mまで高度あげてから1800mまで下り、また更に2500mまで登り返すのはキツイ。
しかも事前情報では北鎌沢は右俣と左俣に分かれてるので、主流の左俣ではない右俣に進路を変更し、遡上していくとあった。
涸れている右に右に・・・

って・・・台風の影響か涸れてるどころかジャンジャン水が流れ落ち、どこが支流なのか本流なのか全然分からない。
明らかに自分が集めた事前情報とは違う水量。頭の上からも沢水が降ってきて、完全に沢登り状態。
本当にここなのか・・・?
2度ほど沢の選択を間違え、ブッシュをトラバース。
登山道ではないので、間違えたかどうかは分からないが、帰ってきた今思うと間違えたと思った勘は間違ってなかったんだろう。
でもトラバースは怖い。これまでの山の経験からも相当気を付けないといけない。
急がば回れ。ショートカットは厳禁。今まで散々怖い思いをしてきた。
それでも体力と時間の関係もあり、今回は足元が見えないままブッシュに突っ込んでいった。
しばらく進んだところで、直感的にこれ以上はヤバい・・・と思いトラバースを中断、下り返して正規のラインに戻った事があったが、後からそこを見上げたら5mほどキレ落ちていてゾッとした。あと数歩前に進んでいたらさようならだった。
あと、120cmほどの石に右足を置き体重をかけたら、その石ごと沢に落ちた。
石は2m弱下に落ち止まったが、まさかこんな大きな石まで落ちるとは。
随分台風の影響が出ているんだろう、この先慎重に行かないと。と思った出来事。
自分はとっさに右肩を岩にこすりつけ1m程度の落下ですんだが、左薬指と小指をしこたま打ち付け腫れ上がる。激痛に折れたかな?と一瞬思ったが腫れは1日でひいた。
14:50 北鎌のコル
豪雨で松の倒木が行く手を遮り、ジャンジャン流れる北鎌沢右俣との格闘は終わり、ひょっこりと尾根沿いに出た。
約3時間の急登遡上。
写真で見た場所。見覚えがあった。
ホッとした。

この時点で疲労はピーク。
もう動きたくない・・・
そんな気持ちになったが、実は今回の山行を成功させるポイントは初日にあると考えてた。
核心部はもちろん2日目の北鎌尾根歩きになるが、そこをどれだけ体力を温存した状態で登れるか。
どれだけ1日目に進めるかが今回の鍵。
歩くことに決めた。
沢登りで気付かなかったが、その頃には雨も止んで北鎌のコルからは大天井岳が見事に見えた。
数年前にいくみんと一緒に登った山。
その風景に元気付けられながら重いザックを担ぎ直し、さらに重い足を前に進めた。
ここからが正念場。
そんな気持ちで歩いた。

16:30 P8(ピーク8)
疲労困憊。
出来れば独標と呼ばれる基部まで歩みを進めたかったが、ここで本日の行動を止めることにした。
この先は厳しい箇所が幾度も出てくるはずで、この体力では心許ない。もう自分は北鎌尾根にいる。
精神的疲労と、激しいアップダウンを繰り返し11時間歩き続けた体は止まれサインをずいぶん以前から出していた。
目的地には到達しなかったけれど、よく頑張ったと思う。
独標は霧に見え隠れ。

P8のピークで幕営するためにザックから荷物を取り出したときにまたやっちまった事に気付く。
ザックカバーはしていたが、雨と沢登でダウンジャケットとダウンシュラフを濡らすという失態。
いくら夏山とはいえ、強風の3000m近くの尾根上でダウンの濡れは死に近づく。
P8のピークで低木にダウンを引っ掛け、強風により少しでも乾かした。。。
こんなところで・・・鯉のぼりみたいやんけー・・・と少し情けなかった。
P8からの眺め

幕営地

ぎりぎりテントを張れる広さ。というか、ちょっと小さい。
テント幕営完了。でも狭くてペグとかちゃんと効いてない個所も。

テントを設営してからはサクサクッと夕食を食べ、19時前には明日に備えて寝た。
多少晴れてた天候も夕方以降は強風とガスに覆われ、眺望はほぼ無し。
一晩中強風にあおられ、テントごと飛ばされそうな夜。
テントのペグが強風で抜けてる事は分かっていたが、直しに外に出たとたんにテントが飛ぶだろうな、と自ら重しと化した。
誰もいない夜なのに、強風がテントに叩き付ける音がなぜか時おり子供の騒ぎ声に聞こえたりするのを気にしつつ、寝袋に包まったまま念仏のように『今はとにかく体力を回復させること。今はとにかく体力を回復させること。』と思いながら夜を過ごした。
この強風だけど、明日はどうか晴れますように・・・
翌日へ続く・・・
気を抜けば死ねる場所だらけの北鎌尾根。
そして暴風雨でアクシデントが重なり危険な山行となりました。
北鎌尾根へのルート
■8月10日(日)
台風11号が通り過ぎた18時に自宅を出発し、アカンダナ駐車場に向かう。
でも岐阜県に入り豪雨にさらされる。あれなんかおかしいなぁ。
目的地は北アルプス、北鎌尾根からの槍ヶ岳。
一般登山道ではないバリエーションルート。
22時過ぎにアカンダナ駐車場付近に到着するが、03時にしか駐車場は開かず、平湯温泉の駐車場で仮眠。
半袖半ズボンで寝たら寒くて何度も起きるが、着込む気力なし。
何より軽トラのボディーを打つ雨音がやる気をそぐ。
■8月11日(月)
台風一過はどこへやら。
アカンダナ駐車場に04時に入場し、始発の04:50の上高地行バスを待っている時点で諦めてレインウェアを着込む。
雨は降り続く。
05:30 上高地出発
今回の山行の目的は北鎌尾根からの槍登頂。
槍ヶ岳が目的ではなく、あくまで目的は北鎌尾根。
しかも1泊2日の強行軍なので初日はとにかく距離を伸ばしたい。
08:40 槍沢ロッヂ
雨は降り続くどころか、ますます強雨に。
休憩もそこそこに先を急ぐ。
他の登山者も「台風一過だと思ったのになぁー」と話してる。
09:30 槍沢大曲
槍ヶ岳が目的ならこのまま真っ直ぐに殺生ヒュッテに向かうが、今回は大曲から水俣乗越を目指す。
10:30 水俣乗越
標高2500mほど。上高地から1000mほど高度を上げる。
ここまでが一般登山道。
ここからは登山道ではないバリエーションの世界。
全ては自己責任。
水俣乗越から登山道を外れ、北に進路をとり下る。
下り道はザレザレで、撤退の時にここを登り返すはキツイな・・・と思いながら下る。
途中には遭難者の物なのか、ずいぶん以前と思われる登山靴が片足だけ落ちてたり、ちょっと気味が悪い。
そんなところに雨が降る中、足を踏み入れていく自分も自分。
今回の山行は自分なりの挑戦。
途中雪渓も下り、標高をどんどん下げて1800m地点まで。
大きなアクシデントが1つ。
雨のせいか天候のせいかiPhoneのGPSが調子悪く感度が全然上がらない。(結局、我がiPhoneこの山行で息絶える・・・)
なにせ単独行が主の自分は、このGPSに助けてもらってる部分が多く、これがないと大幅な戦力ダウン。
バリエーションのルートに入っているので自分がどこを歩いてるのか、GPSが無いと方角と地図だけで判断しないといけなくなる。
なにせ登山道を歩いてるわけじゃないのだから。
上高地からずっと調子の悪かったiPhone GPSを頼むぞ!と祈るような気持ちで何度も見たが、回復する兆しなし。
それどころか表示される現在地がフラフラと彷徨っており、不安をさらにあおる。
もうこのGPSには頼れない。
こんな事もあろうかと事前に情報収集し、プリントアウトしていた紙を取り出す。
悲惨。
インクが汗と雨でにじんで何が何だかさっぱり分からない・・・
ぴーんち!
いや、冗談じゃなくピンチ。
大体、ここまで雨になるなんて思ってなかったもんなぁ…
もうこれで頼れるのは山岳地図だけ。
あとは自分の記憶にある知識。
12:00 北鎌沢出会
高度を1800mほどまで下げた場所に、今下ってきた主流の天上沢と北鎌沢が出会う北鎌沢出会がある。
といっても通常の登山道のような標識はないので、たぶんここがそうだな、と思うだけ。
予定してるルートはここから北鎌沢に進路を変更する。
山岳地図の等高線と、霧雨でかすんではいるが時折見える地形から判断した。
何せバリエーションのルートで、平日で、さらに天気が悪い条件なので、ひとっこひとり遭わない。
いれば聞けるのに、誰もいない。
台風の雨で増水してると思われる沢の轟音が聞こえるだけ。
とにかく不安。
ここで良いのか?
本当にここなのか?
大丈夫か自分!!
通常ならここの北鎌沢出会で幕営するんじゃなかろうか。
テント泊の装備を担いで上高地から歩いてきて12時。
ここが北鎌沢出会かどうかも怪しく、ここから先に進めば標高はまた2500mほどまで上げないといけない。
当然歩いたこともない北鎌沢。道迷いがひじょうに多いと言われている北鎌沢。
もう勝負勝負!
自分を信じろ!
北鎌沢出会を後にし、西に進路を変更、北鎌沢を遡上する。
1500mから2500mまで高度あげてから1800mまで下り、また更に2500mまで登り返すのはキツイ。
しかも事前情報では北鎌沢は右俣と左俣に分かれてるので、主流の左俣ではない右俣に進路を変更し、遡上していくとあった。
涸れている右に右に・・・
って・・・台風の影響か涸れてるどころかジャンジャン水が流れ落ち、どこが支流なのか本流なのか全然分からない。
明らかに自分が集めた事前情報とは違う水量。頭の上からも沢水が降ってきて、完全に沢登り状態。
本当にここなのか・・・?
2度ほど沢の選択を間違え、ブッシュをトラバース。
登山道ではないので、間違えたかどうかは分からないが、帰ってきた今思うと間違えたと思った勘は間違ってなかったんだろう。
でもトラバースは怖い。これまでの山の経験からも相当気を付けないといけない。
急がば回れ。ショートカットは厳禁。今まで散々怖い思いをしてきた。
それでも体力と時間の関係もあり、今回は足元が見えないままブッシュに突っ込んでいった。
しばらく進んだところで、直感的にこれ以上はヤバい・・・と思いトラバースを中断、下り返して正規のラインに戻った事があったが、後からそこを見上げたら5mほどキレ落ちていてゾッとした。あと数歩前に進んでいたらさようならだった。
あと、120cmほどの石に右足を置き体重をかけたら、その石ごと沢に落ちた。
石は2m弱下に落ち止まったが、まさかこんな大きな石まで落ちるとは。
随分台風の影響が出ているんだろう、この先慎重に行かないと。と思った出来事。
自分はとっさに右肩を岩にこすりつけ1m程度の落下ですんだが、左薬指と小指をしこたま打ち付け腫れ上がる。激痛に折れたかな?と一瞬思ったが腫れは1日でひいた。
14:50 北鎌のコル
豪雨で松の倒木が行く手を遮り、ジャンジャン流れる北鎌沢右俣との格闘は終わり、ひょっこりと尾根沿いに出た。
約3時間の急登遡上。
写真で見た場所。見覚えがあった。
ホッとした。
この時点で疲労はピーク。
もう動きたくない・・・
そんな気持ちになったが、実は今回の山行を成功させるポイントは初日にあると考えてた。
核心部はもちろん2日目の北鎌尾根歩きになるが、そこをどれだけ体力を温存した状態で登れるか。
どれだけ1日目に進めるかが今回の鍵。
歩くことに決めた。
沢登りで気付かなかったが、その頃には雨も止んで北鎌のコルからは大天井岳が見事に見えた。
数年前にいくみんと一緒に登った山。
その風景に元気付けられながら重いザックを担ぎ直し、さらに重い足を前に進めた。
ここからが正念場。
そんな気持ちで歩いた。
16:30 P8(ピーク8)
疲労困憊。
出来れば独標と呼ばれる基部まで歩みを進めたかったが、ここで本日の行動を止めることにした。
この先は厳しい箇所が幾度も出てくるはずで、この体力では心許ない。もう自分は北鎌尾根にいる。
精神的疲労と、激しいアップダウンを繰り返し11時間歩き続けた体は止まれサインをずいぶん以前から出していた。
目的地には到達しなかったけれど、よく頑張ったと思う。
独標は霧に見え隠れ。
P8のピークで幕営するためにザックから荷物を取り出したときにまたやっちまった事に気付く。
ザックカバーはしていたが、雨と沢登でダウンジャケットとダウンシュラフを濡らすという失態。
いくら夏山とはいえ、強風の3000m近くの尾根上でダウンの濡れは死に近づく。
P8のピークで低木にダウンを引っ掛け、強風により少しでも乾かした。。。
こんなところで・・・鯉のぼりみたいやんけー・・・と少し情けなかった。
P8からの眺め
幕営地
ぎりぎりテントを張れる広さ。というか、ちょっと小さい。
テント幕営完了。でも狭くてペグとかちゃんと効いてない個所も。
テントを設営してからはサクサクッと夕食を食べ、19時前には明日に備えて寝た。
多少晴れてた天候も夕方以降は強風とガスに覆われ、眺望はほぼ無し。
一晩中強風にあおられ、テントごと飛ばされそうな夜。
テントのペグが強風で抜けてる事は分かっていたが、直しに外に出たとたんにテントが飛ぶだろうな、と自ら重しと化した。
誰もいない夜なのに、強風がテントに叩き付ける音がなぜか時おり子供の騒ぎ声に聞こえたりするのを気にしつつ、寝袋に包まったまま念仏のように『今はとにかく体力を回復させること。今はとにかく体力を回復させること。』と思いながら夜を過ごした。
この強風だけど、明日はどうか晴れますように・・・
翌日へ続く・・・
2014年08月12日
山の厳しさ
台風11号により週末の予定を変更せざるおえなくなり、急遽無理言って月曜日と火曜日を休暇にしてもらう。
全力で挑んだ山行。
今は満身創痍。
指も手も、足も胸も肩も全部痛い。
稜線上では暴風雨にさらされた。
雨でGPS機能を喪失し、自分なりにまとめた地形図メモも雨で判読不能。
頼れるのは自分の頭と山岳地図、そして経験。
もう一度この場所に行こうとは今は思えないわ。
全力で挑んだ山行。
今は満身創痍。
指も手も、足も胸も肩も全部痛い。
稜線上では暴風雨にさらされた。
雨でGPS機能を喪失し、自分なりにまとめた地形図メモも雨で判読不能。
頼れるのは自分の頭と山岳地図、そして経験。
もう一度この場所に行こうとは今は思えないわ。
2010年07月22日
登山 ジャンダルム その5
2日目のルートマップ

■7月18日(2日目 大キレットへ)
02時過ぎに目が覚めるものの、辺りは真っ暗。
しばらくウトウトしていたら外が騒がしい。
どうも隣のテントのアベックがどうも撤収作業を始めたらしい。
まだ早いやろ・・・と思いつつ外の物音を聞いてると更にそのとなりも撤収作業開始。
また出遅れたか
慌てて外に出たらすでに幾つかのテントは無い。
山の朝は早いなー。まだ暗闇やで・・・。
飯の準備をしながらテント撤収作業に入る。
自分も今日は大キレット越え。
大キレットがどんな場所か知らないが、早く出るに越した事はない。
そうこうしてる間にも準備を整えた登山者が自分の横をすり抜けて出発していく。
ぬおー!なんでそんなに準備早いんじゃー・・・
皆さん慣れてるのか知らんけど、撤収作業が早い!
自分より後に準備し始めた人達もどんどん旅立つ。
青メガネ氏もその一人で、準備しだしたなぁーと思ったら、すぐ旅立った。
ううう・・・明日はもっと効率良く撤収作業しないとな・・・と思ったわ。
撤収準備も終わりに近付いた頃、東の空が明るくなってきた。
場所を移動するとすでに小屋泊まりの人達が御来光を見るためにたくさん外に。
槍ヶ岳の奥に上がる御来光。今日は天気が良さそうじゃー

05:00 槍ヶ岳山荘出発。
今日はそのまま昨日のルートで下りると言っていた黄フリース氏とはここでお別れ。
準備中の黄フリース氏に挨拶とお礼だけして出発した。
またどこかでバッタリ会えるのを楽しみにしています。
出発時に撮った笠ヶ岳。頂上付近に朝日が当たってきれい。

今日はこのまま南下して最終的には穂高岳山荘を目指す。
コースタイム的には9時間半といったところ。
とりあえずの目標は南岳山荘。そしてその先にあるのが大キレットだ。
05:13 視界から消えそうになる槍ヶ岳を
槍ヶ岳山荘のテン場にはまだカラフルなテントが見える。

稜線に沿って南に少し歩いたら昨日まで見えなかった風景が。
ここからは見るものすべてが新鮮。色が違って面白い山だなーと
知識が無いので何山なのかさっぱり分からん
(実は自分が登った事もある山も含まれていたのにね )
)

西側を見ると笠ヶ岳の奥にも山脈が。さすがにこれは分かる。白山だ。
地元から最も近い高山だが、こんなにハッキリ見えたのは初めて。嬉しい

そしてそして東側にはとんがり山。この日はずっとこの山を見て歩いたな。
なんて山なんだろうなーって思いながらの一日。形の良い、とんがり山だ

05:37 中岳頂上付近で振り返って撮った槍ヶ岳。
飛騨側(西)はさほど無いが、信州側(東)にはまだ雪渓がたっぷり。

そしてこの後、ルートを見失う。
いくら探してもマーキングが無い。
実際にはきっちりマーキングが付いていたんだが、見えてない。
まったく視界に入ってない。
自分の中では今日は南下していかないといけないという潜在意識で行動してるので、南側ばかり捜索する。何度も行ったり来たりして時間を浪費。一旦パスした人にも追いつかれ「マーキングが無いんですよぉ」と言うと、「そうなんですか?でもまぁ、稜線に沿って歩けば良いんですよね?」と東側の稜線を指差して言う。
(・・・あっ!?)
情けないというか何というか・・・。
なんでもそうだけど、思い込みって怖い。
視界には入ってるはずなのに見えなくなる。こうやって遭難するのかな?
まぁ、おかしいなと思った時に引き返してきたのは良い判断だった。
そういう事にしておこう
06:17 その後は順調にマイペースを通し、南岳山頂到着。
まぁここは通過点なのでそのまま下りに入ると人影が見えた。
今日は体調も良く何人もの人をパスしてきたので別に珍しくないが、この人は知ってる。
青メガネ氏だ。ようやく追いついた。この人も早いなー。
06:21 最初の目的地、南岳小屋に到着。青メガネ氏とほぼ同時。
青メガネ氏のこの日の目的地は昨日聞いたので知ってる。穂高岳山荘、自分と一緒だ。
青メガネ氏はここで着替え休憩を取る様子。
自分はここで水の補給をする予定だったのだが、南岳小屋、なんだかひっそりとしていて営業してるのか?って状況。(いや、実際ここに泊まった人に逢ってるから間違いなく営業してたのだけど・・・)そのまま素通りする事にした。
南岳小屋付近から撮った大キレット。いよいよ本日の核心部、大キレットを越える。
うへー、こんなに下りるん?こんだけ下りたらまた登らんとアカンのやで

後ろを振り返ると着替えを終えた青メガネ氏もザックを背負い出してる。
さ、自分も出発しよう!
最初の崖を下っていく。
獅子鼻岩という場所らしいが、ほとんど垂直に近い場所を鎖・ハシゴを使い下る。
そしてまた知ってる人物と遭遇。
Canon一眼を携えた好青年、ま~やんだ。(もちろんまだ名前は知らない)
追いついたらあっさり道を譲ってくれたのでそのまま下降。
ま~やん、槍ヶ岳のテン場を03時半に出発し、御来光の撮影に興じていたらしい。
ハシゴ付近では下から登ってくる登山者に会う。
崖の途中でヤンキー座りで登りを待ちながら、その人に「ここの登りはキツイですねー」と言ったら「いやいやここを下る方がキツイでしょー」と言われた。
(ふ~ん、そうなの?)と思いつつその場をやり過ごしたが、その後逢う人逢う人、下りの方がキツイ、怖い、と言っていた。
この山行で分ったのは、どうも自分は崖を下るのが好きみたい。
逆に苦手なのが足だけで登る坂
崖を下りて振り返って見る獅子鼻岩。
・・・どこをどう見たら獅子鼻なんだろうか・・・

そして長谷川ピークと呼ばれる付近の岩場。飛騨側に落ちたらサヨウナラー
ただ写真で見るほど現場を歩くとそうでもない。

長谷川ピークを抜け、そのまま順調にマイペースで行くと3人組のパーティに追い付いた。
先頭が30代後半の女性、続いて50代半ばの男性、最後に男性と同年代のリーダー的な女性。
こっちのペースと3人パーティーのペースはまったく違うのだが、追い付いた場所が悪かった。
リーダー的な女性が「(すれ違う)場所があれば行って頂きますから、ここはゆっくり行かせてあげてください」と言ってきた。もちろんすれ違う場所もないし、なにより先頭の女性の動きを見て(急かせたらマズイな)と直感的にも感じた。とにかく体の動きが不安定で見てるほうが怖かった。

今、これを書きながら調べると、追い付いた場所はどうも飛騨泣きと呼ばれる大キレット中の難所らしい。リーダー的な女性はそこが飛騨泣きである事を知っていたんだろう。それが「ここはゆっくり」という言葉に表れてる。
飛騨泣きをゆっくり越えた後すれ違わせてもらい、自分はまたマイペースで北穂高山荘を目指す。
大キレットも残りわずか。
北穂高山荘までの最後の崖を登る。
この辺りからは山荘から下りてくる登山者がグッと増え、落石に注意して歩いた。
落石については、このジャンダルム挑戦登山にあたりヘルメットの購入を本気で考えた。
ただいかんせん値段が高い。今後の使用頻度もそう高くないと思うし、テン泊でただでさえ荷物が多いのに更に増やすのか?う~ん、視界も遮られるかもしれんしな・・・と言い訳を考えながら結局買わずにこの登山を迎えてしまった。
現場で実感した個人的な感想を書くと、基本的な事を守れればヘルメットは不要かもしれない。
もちろんあるに越した事はないが、落石って基本的に人間が起こす。
基本というのは、そういう場所に最初から自分の身を置かないこと。
崖では人の下に入らない事。
ハシゴも一緒。
こんな基本的な事だけど、今回の登山ではそれが出来てない人が非常に多く驚いた。
ハシゴでは(あのー、上の人が落ちてきたらあなたも一緒に死にますよ・・・)って思った事が何度かあった。
想像力を働かせる。自分の身は自分で守る。
私も登山用に習ったわけじゃないが、想像すれば当たり前に分ることだと思う。
ただ人が増えてくれば知らない間に上に人がいる事もある。
それを避けるためにも早立ち早着きし、危険箇所で渋滞するリスクを避ける。
こういう人気のあるアルプス登山では基本の重要性を身を持って感じた次第。
08:15 北穂高山荘到着。着いた着いたー!大キレット抜けたー
槍ヶ岳山荘を5時に出て3時間ちょいで着いた。
予定より全然早く着いたし、今後の余裕も出て来た。
こりゃーここで大休憩だな と調子に乗る。
と調子に乗る。
向かった先は売店だ。もちろん 。生ビールだー
。生ビールだー
昨日飲めなかった生ビールを800円でいただく。
休憩していた外人さんに「ココデノム ナマビールハ サイコーネ!」と話しかけられ、どう応えて良いか分からんけどとにかく親指上げて満面の笑みで返した
この行動、この時点で完全に調子に乗っていたものと思われる。

いやー、ここの眺めは最高だぁ
大キレット抜けて今日の仕事は終~了~くらいの勢いで自分が歩いて来た稜線越しに見る槍ヶ岳を眺めながらビールをあおる。いやー最高だぁ
ちょっと移動すれば笠ヶ岳もばっちり。

今回の山行で立ち寄った山小屋の中では個人的にここが一番。良い小屋だぁ。
気に入ったついでに山小屋バッチと手ぬぐいまで購入した。
うん、完全に調子に乗っていた。。。
私は靴下まで脱いで完全リラックス状態。
後ろの若いカップルの話が聞こえてくる。
「今日は1人1枚の布団で寝れると良いね」と可愛く話す彼女に「無理だね」と冷たく突き放す彼氏。
(よほど嫌なことあったのかな?ちょっとキレてます? )
)
山の経験が余りなさそうな彼女の沈んだ声がとても印象的だった。
やはり昨日は沢山の人でごった返したみたいだ。
今後もテントを担いで登ろう、と心に決めた瞬間だった
30分ほど休んでいると、先ほど飛騨泣きですれ違った3人パーティーが上がって来た。
目が合ったので挨拶すると30代後半の女性が「おつかれー 」とめっちゃテンション高い。大キレット超えの嬉しさが伝わる。良いねぇ。
」とめっちゃテンション高い。大キレット超えの嬉しさが伝わる。良いねぇ。
この時点での休憩者は数人で、3人のテンション上がりまくった声はどこに居ても聞こえる。
リーダー的な女性が「○○ちゃん良かったねー!やっぱり去年は何かが足りなかったって事なのよー!」と話してた。たぶん去年大キレットに挑戦して途中棄権したんだろうな。
あまりに充実感に溢れていたので、大キレットをバックに写真撮りましょうか?と話しかけると、リーダー的な女性が「昨日どこかでお会いしましたよね?」と言う。
・・・知らんなぁ
「そのハンティングの帽子、どっかで見覚えがあるんだけどなぁ・・・」と言われ思い出した。
昨日、飛騨乗越を疲労困憊で登って来た時、「大キレットを抜けられて来たんですか?」と話しかけられた3人組のパーティーだ。
話すとその後は南岳山荘に小屋泊まりして、大キレットに備えたそうな。
大キレットを越える!というのがこの山行の大目標だったんだなぁ。おめ
そしてそのテンションのまま「さぁ下りよう!」って出発していった。
ここからだと・・・北穂の分岐で涸沢の方に下りるのかな?
その3人組を撮ってあげたお礼に撮ってくれた写真。
あの尖がってる槍ヶ岳からこの稜線を歩いて来たんだなぁ

今回、お金が無くて買えなかった物に帽子がある。
これはどっかで1000円程で買った普通の帽子だけど、山では目立つ。
みんな山用のシャカシャカした素材の帽子を格好良く被ってる。
最初はちょっと恥ずかしかったけど、今回この帽子のおかげで何人かの人に覚えていてもらった。
これはこのまま突き通しても面白いかもしれない
そしてまたしばらくすると青メガネ氏とま~やんがほぼ同時に上がって来た。
お疲れ様の意味を込めた会釈をすると、青メガネ氏が自分の斜め前に座った。
「歩くの早いですね」と言われ、「今日は体調が良いですわ。昨日はあなたのペースに付いて行ってバテましたけど 」とそんな会話から始まり10分ほど話した。
」とそんな会話から始まり10分ほど話した。
そしてこれからの予定を確認。
今日は穂高岳山荘に泊まって、明日前穂高から上高地に下りてバスで新穂高温泉の駐車場に帰るという事だった。
気が付けば09時を過ぎてる・・・約1時間の大休憩だ。
知らない間に北穂高山荘のデッキにも人が溢れていた。人込みは苦手。
青メガネ氏に先に出発する事を告げ、ザックを担いだ。
その青メガネ氏もすぐに出発する体勢だった。
目指すは涸沢岳を越え、その先にある穂高岳山荘。本日の最終目的地だ。
大キレット抜けた今、今日はもう他に何も不安はないと思っていた。
ビール飲んで調子こいた代償がこの直後に訪れる・・・。
その6へ続く
(って長げーなコレ )
)
■7月18日(2日目 大キレットへ)
02時過ぎに目が覚めるものの、辺りは真っ暗。
しばらくウトウトしていたら外が騒がしい。
どうも隣のテントのアベックがどうも撤収作業を始めたらしい。
まだ早いやろ・・・と思いつつ外の物音を聞いてると更にそのとなりも撤収作業開始。
また出遅れたか

慌てて外に出たらすでに幾つかのテントは無い。
山の朝は早いなー。まだ暗闇やで・・・。
飯の準備をしながらテント撤収作業に入る。
自分も今日は大キレット越え。
大キレットがどんな場所か知らないが、早く出るに越した事はない。
そうこうしてる間にも準備を整えた登山者が自分の横をすり抜けて出発していく。
ぬおー!なんでそんなに準備早いんじゃー・・・

皆さん慣れてるのか知らんけど、撤収作業が早い!
自分より後に準備し始めた人達もどんどん旅立つ。
青メガネ氏もその一人で、準備しだしたなぁーと思ったら、すぐ旅立った。
ううう・・・明日はもっと効率良く撤収作業しないとな・・・と思ったわ。
撤収準備も終わりに近付いた頃、東の空が明るくなってきた。
場所を移動するとすでに小屋泊まりの人達が御来光を見るためにたくさん外に。
槍ヶ岳の奥に上がる御来光。今日は天気が良さそうじゃー

05:00 槍ヶ岳山荘出発。
今日はそのまま昨日のルートで下りると言っていた黄フリース氏とはここでお別れ。
準備中の黄フリース氏に挨拶とお礼だけして出発した。
またどこかでバッタリ会えるのを楽しみにしています。
出発時に撮った笠ヶ岳。頂上付近に朝日が当たってきれい。
今日はこのまま南下して最終的には穂高岳山荘を目指す。
コースタイム的には9時間半といったところ。
とりあえずの目標は南岳山荘。そしてその先にあるのが大キレットだ。
05:13 視界から消えそうになる槍ヶ岳を

槍ヶ岳山荘のテン場にはまだカラフルなテントが見える。
稜線に沿って南に少し歩いたら昨日まで見えなかった風景が。
ここからは見るものすべてが新鮮。色が違って面白い山だなーと

知識が無いので何山なのかさっぱり分からん

(実は自分が登った事もある山も含まれていたのにね
 )
)西側を見ると笠ヶ岳の奥にも山脈が。さすがにこれは分かる。白山だ。
地元から最も近い高山だが、こんなにハッキリ見えたのは初めて。嬉しい

そしてそして東側にはとんがり山。この日はずっとこの山を見て歩いたな。
なんて山なんだろうなーって思いながらの一日。形の良い、とんがり山だ

05:37 中岳頂上付近で振り返って撮った槍ヶ岳。
飛騨側(西)はさほど無いが、信州側(東)にはまだ雪渓がたっぷり。
そしてこの後、ルートを見失う。
いくら探してもマーキングが無い。
実際にはきっちりマーキングが付いていたんだが、見えてない。
まったく視界に入ってない。
自分の中では今日は南下していかないといけないという潜在意識で行動してるので、南側ばかり捜索する。何度も行ったり来たりして時間を浪費。一旦パスした人にも追いつかれ「マーキングが無いんですよぉ」と言うと、「そうなんですか?でもまぁ、稜線に沿って歩けば良いんですよね?」と東側の稜線を指差して言う。
(・・・あっ!?)
情けないというか何というか・・・。
なんでもそうだけど、思い込みって怖い。
視界には入ってるはずなのに見えなくなる。こうやって遭難するのかな?
まぁ、おかしいなと思った時に引き返してきたのは良い判断だった。
そういう事にしておこう

06:17 その後は順調にマイペースを通し、南岳山頂到着。
まぁここは通過点なのでそのまま下りに入ると人影が見えた。
今日は体調も良く何人もの人をパスしてきたので別に珍しくないが、この人は知ってる。
青メガネ氏だ。ようやく追いついた。この人も早いなー。
06:21 最初の目的地、南岳小屋に到着。青メガネ氏とほぼ同時。
青メガネ氏のこの日の目的地は昨日聞いたので知ってる。穂高岳山荘、自分と一緒だ。
青メガネ氏はここで着替え休憩を取る様子。
自分はここで水の補給をする予定だったのだが、南岳小屋、なんだかひっそりとしていて営業してるのか?って状況。(いや、実際ここに泊まった人に逢ってるから間違いなく営業してたのだけど・・・)そのまま素通りする事にした。
南岳小屋付近から撮った大キレット。いよいよ本日の核心部、大キレットを越える。
うへー、こんなに下りるん?こんだけ下りたらまた登らんとアカンのやで

後ろを振り返ると着替えを終えた青メガネ氏もザックを背負い出してる。
さ、自分も出発しよう!
最初の崖を下っていく。
獅子鼻岩という場所らしいが、ほとんど垂直に近い場所を鎖・ハシゴを使い下る。
そしてまた知ってる人物と遭遇。
Canon一眼を携えた好青年、ま~やんだ。(もちろんまだ名前は知らない)
追いついたらあっさり道を譲ってくれたのでそのまま下降。
ま~やん、槍ヶ岳のテン場を03時半に出発し、御来光の撮影に興じていたらしい。
ハシゴ付近では下から登ってくる登山者に会う。
崖の途中でヤンキー座りで登りを待ちながら、その人に「ここの登りはキツイですねー」と言ったら「いやいやここを下る方がキツイでしょー」と言われた。
(ふ~ん、そうなの?)と思いつつその場をやり過ごしたが、その後逢う人逢う人、下りの方がキツイ、怖い、と言っていた。
この山行で分ったのは、どうも自分は崖を下るのが好きみたい。
逆に苦手なのが足だけで登る坂

崖を下りて振り返って見る獅子鼻岩。
・・・どこをどう見たら獅子鼻なんだろうか・・・

そして長谷川ピークと呼ばれる付近の岩場。飛騨側に落ちたらサヨウナラー

ただ写真で見るほど現場を歩くとそうでもない。
長谷川ピークを抜け、そのまま順調にマイペースで行くと3人組のパーティに追い付いた。
先頭が30代後半の女性、続いて50代半ばの男性、最後に男性と同年代のリーダー的な女性。
こっちのペースと3人パーティーのペースはまったく違うのだが、追い付いた場所が悪かった。
リーダー的な女性が「(すれ違う)場所があれば行って頂きますから、ここはゆっくり行かせてあげてください」と言ってきた。もちろんすれ違う場所もないし、なにより先頭の女性の動きを見て(急かせたらマズイな)と直感的にも感じた。とにかく体の動きが不安定で見てるほうが怖かった。
今、これを書きながら調べると、追い付いた場所はどうも飛騨泣きと呼ばれる大キレット中の難所らしい。リーダー的な女性はそこが飛騨泣きである事を知っていたんだろう。それが「ここはゆっくり」という言葉に表れてる。
飛騨泣きをゆっくり越えた後すれ違わせてもらい、自分はまたマイペースで北穂高山荘を目指す。
大キレットも残りわずか。
北穂高山荘までの最後の崖を登る。
この辺りからは山荘から下りてくる登山者がグッと増え、落石に注意して歩いた。
落石については、このジャンダルム挑戦登山にあたりヘルメットの購入を本気で考えた。
ただいかんせん値段が高い。今後の使用頻度もそう高くないと思うし、テン泊でただでさえ荷物が多いのに更に増やすのか?う~ん、視界も遮られるかもしれんしな・・・と言い訳を考えながら結局買わずにこの登山を迎えてしまった。
現場で実感した個人的な感想を書くと、基本的な事を守れればヘルメットは不要かもしれない。
もちろんあるに越した事はないが、落石って基本的に人間が起こす。
基本というのは、そういう場所に最初から自分の身を置かないこと。
崖では人の下に入らない事。
ハシゴも一緒。
こんな基本的な事だけど、今回の登山ではそれが出来てない人が非常に多く驚いた。
ハシゴでは(あのー、上の人が落ちてきたらあなたも一緒に死にますよ・・・)って思った事が何度かあった。
想像力を働かせる。自分の身は自分で守る。
私も登山用に習ったわけじゃないが、想像すれば当たり前に分ることだと思う。
ただ人が増えてくれば知らない間に上に人がいる事もある。
それを避けるためにも早立ち早着きし、危険箇所で渋滞するリスクを避ける。
こういう人気のあるアルプス登山では基本の重要性を身を持って感じた次第。
08:15 北穂高山荘到着。着いた着いたー!大キレット抜けたー

槍ヶ岳山荘を5時に出て3時間ちょいで着いた。
予定より全然早く着いたし、今後の余裕も出て来た。
こりゃーここで大休憩だな
 と調子に乗る。
と調子に乗る。向かった先は売店だ。もちろん
 。生ビールだー
。生ビールだー
昨日飲めなかった生ビールを800円でいただく。
休憩していた外人さんに「ココデノム ナマビールハ サイコーネ!」と話しかけられ、どう応えて良いか分からんけどとにかく親指上げて満面の笑みで返した

この行動、この時点で完全に調子に乗っていたものと思われる。
いやー、ここの眺めは最高だぁ

大キレット抜けて今日の仕事は終~了~くらいの勢いで自分が歩いて来た稜線越しに見る槍ヶ岳を眺めながらビールをあおる。いやー最高だぁ

ちょっと移動すれば笠ヶ岳もばっちり。
今回の山行で立ち寄った山小屋の中では個人的にここが一番。良い小屋だぁ。
気に入ったついでに山小屋バッチと手ぬぐいまで購入した。
うん、完全に調子に乗っていた。。。
私は靴下まで脱いで完全リラックス状態。
後ろの若いカップルの話が聞こえてくる。
「今日は1人1枚の布団で寝れると良いね」と可愛く話す彼女に「無理だね」と冷たく突き放す彼氏。
(よほど嫌なことあったのかな?ちょっとキレてます?
 )
)山の経験が余りなさそうな彼女の沈んだ声がとても印象的だった。
やはり昨日は沢山の人でごった返したみたいだ。
今後もテントを担いで登ろう、と心に決めた瞬間だった

30分ほど休んでいると、先ほど飛騨泣きですれ違った3人パーティーが上がって来た。
目が合ったので挨拶すると30代後半の女性が「おつかれー
 」とめっちゃテンション高い。大キレット超えの嬉しさが伝わる。良いねぇ。
」とめっちゃテンション高い。大キレット超えの嬉しさが伝わる。良いねぇ。この時点での休憩者は数人で、3人のテンション上がりまくった声はどこに居ても聞こえる。
リーダー的な女性が「○○ちゃん良かったねー!やっぱり去年は何かが足りなかったって事なのよー!」と話してた。たぶん去年大キレットに挑戦して途中棄権したんだろうな。
あまりに充実感に溢れていたので、大キレットをバックに写真撮りましょうか?と話しかけると、リーダー的な女性が「昨日どこかでお会いしましたよね?」と言う。
・・・知らんなぁ

「そのハンティングの帽子、どっかで見覚えがあるんだけどなぁ・・・」と言われ思い出した。
昨日、飛騨乗越を疲労困憊で登って来た時、「大キレットを抜けられて来たんですか?」と話しかけられた3人組のパーティーだ。
話すとその後は南岳山荘に小屋泊まりして、大キレットに備えたそうな。
大キレットを越える!というのがこの山行の大目標だったんだなぁ。おめ

そしてそのテンションのまま「さぁ下りよう!」って出発していった。
ここからだと・・・北穂の分岐で涸沢の方に下りるのかな?
その3人組を撮ってあげたお礼に撮ってくれた写真。
あの尖がってる槍ヶ岳からこの稜線を歩いて来たんだなぁ

今回、お金が無くて買えなかった物に帽子がある。
これはどっかで1000円程で買った普通の帽子だけど、山では目立つ。
みんな山用のシャカシャカした素材の帽子を格好良く被ってる。
最初はちょっと恥ずかしかったけど、今回この帽子のおかげで何人かの人に覚えていてもらった。
これはこのまま突き通しても面白いかもしれない

そしてまたしばらくすると青メガネ氏とま~やんがほぼ同時に上がって来た。
お疲れ様の意味を込めた会釈をすると、青メガネ氏が自分の斜め前に座った。
「歩くの早いですね」と言われ、「今日は体調が良いですわ。昨日はあなたのペースに付いて行ってバテましたけど
 」とそんな会話から始まり10分ほど話した。
」とそんな会話から始まり10分ほど話した。そしてこれからの予定を確認。
今日は穂高岳山荘に泊まって、明日前穂高から上高地に下りてバスで新穂高温泉の駐車場に帰るという事だった。
気が付けば09時を過ぎてる・・・約1時間の大休憩だ。
知らない間に北穂高山荘のデッキにも人が溢れていた。人込みは苦手。
青メガネ氏に先に出発する事を告げ、ザックを担いだ。
その青メガネ氏もすぐに出発する体勢だった。
目指すは涸沢岳を越え、その先にある穂高岳山荘。本日の最終目的地だ。
大キレット抜けた今、今日はもう他に何も不安はないと思っていた。
ビール飲んで調子こいた代償がこの直後に訪れる・・・。
その6へ続く
(って長げーなコレ
 )
) 2010年07月21日
登山 ジャンダルム その4
初日のルートMAP

■17日(初日後半)の続きから
槍ヶ岳からおじさんの超遅ペースに巻き込まれるものの、特に急ぐ理由も無い。
仕方ない、とあきらめて下山途中で写真撮影

こうやって見ると結構きつい下りだなぁ・・・。
超遅おじさんと、青いのがたぶんCanon一眼を携えた好青年的な返答をした人物だ。
名前をま~やんと言う。(もちろんこの時は知らない)
今後、このジャンダルム挑戦登山で最も重要な関係者になる人物。
ま、ゆくゆく紹介するとする。
槍ヶ岳山荘の眼下には殺生ヒュッテが見える。奥の小さいのがヒュッテ大槍。
山小屋ってみんな屋根が赤いんだな。うちのログハウスも赤屋根で同じだなぁ。

青メガネ氏に聞いたところ、槍ヶ岳山荘のテン場は他に比べても狭いらしく場所も良くない。遅く着いてしまうと満員という事もあり、最悪この写真の殺生ヒュッテまで下りてくださいと言われてしまうらしい。
青メガネ氏のあのペース&休憩無しの理由はそれだったそうで、出来るだけ早く目的地の槍ヶ岳山荘に着いてテン場を確保したかったというのが本音で、結構キツかった と言うてた。
と言うてた。
一緒に超遅ペースで下山した後、到着後の楽しみに興じる事とする。
もちろん だー!
だー!
生ビール 、生ビール
、生ビール と探しても見つからない。
と探しても見つからない。
あら?売ってないのかな?と思いつつ、仕方なく自販機でスーパードライを購入。
350ml缶で500円。高いけど、3000mの標高で飲めるビール。この辺は気持ち良く出せる。
缶ビール片手に小屋の外に出たらみんな景色を見ながら生ビール飲んでる。
あら?
おっ、自販機の隣の部屋が食堂だったのね~
槍ヶ岳山荘にも生ビールあります!(ついでに言うと穂高岳山荘にはありませぬ・・・)
やや凹み気味に、景色の良い場所でビールを飲もうとするが席が無い。
どんどん槍ヶ岳から離れて行くと、ようやく男性一人だけが座ってる席が空いていた。
まぁそこで良いわー、と座ったらその男性が黄フリース氏だった。なんとも偶然だ。
当然そこから登山談義に花が咲く。
黄フリーフ氏も単独で、ここに早めに着いてしまったからどうやって時間を潰そうかと悩んでいたらしい。タイミング良くそこに現れたのが自分だったと言う訳で
2時間ほど話し込んだかな?
黄フリース氏は名古屋から来ていて、登山歴15年のベテラン。
新穂高温泉の無料駐車場を03時に出発したらしく、ライトを点けながらトボトボとぼとぼ歩いてきた事。そしてそのトボトボ歩きは、ハイペースで飛ばした挙句、山頂付近で足が痙攣、危険を感じた経験から確立した自分のペースであり、それがピタッとコースタイム通りだと言うこと。
黄フリース氏にはマイペースの重要性を教えて頂いた。
「でもにいちゃん、速いねー」と言いながら、その言葉には余裕がある。
疲労困憊で辿り着いた自分とは雲泥の違い。それが次の日の山行に関わるのだと。
工程を考え時間を計算、出発時間を決定。マイペースを保ち、次の日に疲れを残さない。
山の強者の話すその言葉すべてが教科書だった。
そして雪渓を直登した事もやんわり注意された
2週間前のここでの山行を再度され、10本爪のアイゼンをザックに入れている事。
私が雪渓を登っていくのが見えたが自分は雪渓を迂回した事。
気持ちすべてを見透かされてるようで、恥ずかしかったな
黄フリース氏は槍ヶ岳が大好きなんだそう。
槍ヶ岳は何度も来ており「ガスッて来たし今日はもう良いわ」と言い、「槍を360度色んな方向からから見るのが楽しみなんだ、あと見てないポイントが2箇所残ってる。そこに行くのが今の楽しみだ」とか。お奨めは双六から見る槍ヶ岳と言っていた。
黄フリース氏とは15時前くらいまで話した後、少し横になりたくてテントに戻った。
最初は数箇所しかなかったテントも次第に数が増え、最終的には満員近くまで行った様だ。

手前の赤いのが我がテント。このテン場には赤いテントは自分のだけだった。
テントに関してはどのメーカーが多いとか特に無いねぇ。バラバラ。
自分もどのテントを買うか迷ったけど、自分の好きなのを買えば良いんじゃないかなー。
ただモンベルの黄色いテントはどこのテン場でもいくつかはあったな。
すでにその頃にはガスが出てきて、さっきまで綺麗に見えていた風景はなし。
すぐ近くにある槍ヶ岳すら見えない。
テントの外では雨音がしていて「うわー、早くテント作らんと!」と今到着したばかりのアベックが急いで設営に取り掛かる声。早く着いてよかった。山では早寝早立ちというが、まさに、だ。
そのままテント内でゴロンと横になったらどうも眠ったみたい。
気が付けば17時前になっていた。雨音は消えてた。
テントは他の人に気兼ねなく過ごせるから良いね。
今日の小屋泊まりはキツイだろう。
今後も出来るだけテントを持って山に来よう。
そして夕食。アウトドアショップで買ったアルファ米を食べた。
アルファ米どころか、おしるこや味噌汁含めどんだけ食うねん!
って言うくらい腹いっぺー 食べた。
食べた。
別に腹が空いていた訳じゃない。
とにかく荷物(重り)を減らしたい一心だった
山スカートの女性に抜かれた悲しさに包まれながら、腹減ってもないのに無理やり食べる一人寂しい夕食でしたわ

重さの要因の一つにはこいつもある。
お気に入りのコールマンのフェザーストーブ。
前回のキャンプで使わせてもらったガスストーブの使い勝手が非常に良くて、軽量化を考えて買おうかとも考えた。でもそれだけの事に買うのも・・・。それにこいつと一緒に最初のテント泊がしたかったという気持ちもあった。
・・・今考えれば借りたら良かったな
夕暮れが楽しみだったがガスってしまい、ガスの切れ間から一瞬一瞬、時折見れるだけ。
そして何もする事も無いので、19時には早めの就寝。
明日はあの有名な大キレット越えだ。早く寝て今日の疲れを回復させないと。
(キレットは漢字で切戸と書き、山稜がV字型に深く切れこんで低くなっている場所の意味)
大キレット。
雑誌の言葉を引用すると「国内縦走路では屈指の難路」らしく、飛騨乗越をクリアした先の尾根でおばちゃんに話しかけられた「大キレットを抜けられてきたんですか?」という言葉からもその重みが分かる。
初めて行く難路と呼ばれるコース。
いったいどんな道が待ち構えているんだろうか・・・と思いながら眠りに就いた。
■登山 ジャンダルム 初日終了
その5に続く
■17日(初日後半)の続きから
槍ヶ岳からおじさんの超遅ペースに巻き込まれるものの、特に急ぐ理由も無い。
仕方ない、とあきらめて下山途中で写真撮影

こうやって見ると結構きつい下りだなぁ・・・。
超遅おじさんと、青いのがたぶんCanon一眼を携えた好青年的な返答をした人物だ。
名前をま~やんと言う。(もちろんこの時は知らない)
今後、このジャンダルム挑戦登山で最も重要な関係者になる人物。
ま、ゆくゆく紹介するとする。
槍ヶ岳山荘の眼下には殺生ヒュッテが見える。奥の小さいのがヒュッテ大槍。
山小屋ってみんな屋根が赤いんだな。うちのログハウスも赤屋根で同じだなぁ。
青メガネ氏に聞いたところ、槍ヶ岳山荘のテン場は他に比べても狭いらしく場所も良くない。遅く着いてしまうと満員という事もあり、最悪この写真の殺生ヒュッテまで下りてくださいと言われてしまうらしい。
青メガネ氏のあのペース&休憩無しの理由はそれだったそうで、出来るだけ早く目的地の槍ヶ岳山荘に着いてテン場を確保したかったというのが本音で、結構キツかった
 と言うてた。
と言うてた。一緒に超遅ペースで下山した後、到着後の楽しみに興じる事とする。
もちろん
 だー!
だー!生ビール
 、生ビール
、生ビール と探しても見つからない。
と探しても見つからない。あら?売ってないのかな?と思いつつ、仕方なく自販機でスーパードライを購入。
350ml缶で500円。高いけど、3000mの標高で飲めるビール。この辺は気持ち良く出せる。
缶ビール片手に小屋の外に出たらみんな景色を見ながら生ビール飲んでる。
あら?
おっ、自販機の隣の部屋が食堂だったのね~

槍ヶ岳山荘にも生ビールあります!(ついでに言うと穂高岳山荘にはありませぬ・・・)
やや凹み気味に、景色の良い場所でビールを飲もうとするが席が無い。
どんどん槍ヶ岳から離れて行くと、ようやく男性一人だけが座ってる席が空いていた。
まぁそこで良いわー、と座ったらその男性が黄フリース氏だった。なんとも偶然だ。
当然そこから登山談義に花が咲く。
黄フリーフ氏も単独で、ここに早めに着いてしまったからどうやって時間を潰そうかと悩んでいたらしい。タイミング良くそこに現れたのが自分だったと言う訳で

2時間ほど話し込んだかな?
黄フリース氏は名古屋から来ていて、登山歴15年のベテラン。
新穂高温泉の無料駐車場を03時に出発したらしく、ライトを点けながらトボトボとぼとぼ歩いてきた事。そしてそのトボトボ歩きは、ハイペースで飛ばした挙句、山頂付近で足が痙攣、危険を感じた経験から確立した自分のペースであり、それがピタッとコースタイム通りだと言うこと。
黄フリース氏にはマイペースの重要性を教えて頂いた。
「でもにいちゃん、速いねー」と言いながら、その言葉には余裕がある。
疲労困憊で辿り着いた自分とは雲泥の違い。それが次の日の山行に関わるのだと。
工程を考え時間を計算、出発時間を決定。マイペースを保ち、次の日に疲れを残さない。
山の強者の話すその言葉すべてが教科書だった。
そして雪渓を直登した事もやんわり注意された

2週間前のここでの山行を再度され、10本爪のアイゼンをザックに入れている事。
私が雪渓を登っていくのが見えたが自分は雪渓を迂回した事。
気持ちすべてを見透かされてるようで、恥ずかしかったな

黄フリース氏は槍ヶ岳が大好きなんだそう。
槍ヶ岳は何度も来ており「ガスッて来たし今日はもう良いわ」と言い、「槍を360度色んな方向からから見るのが楽しみなんだ、あと見てないポイントが2箇所残ってる。そこに行くのが今の楽しみだ」とか。お奨めは双六から見る槍ヶ岳と言っていた。
黄フリース氏とは15時前くらいまで話した後、少し横になりたくてテントに戻った。
最初は数箇所しかなかったテントも次第に数が増え、最終的には満員近くまで行った様だ。
手前の赤いのが我がテント。このテン場には赤いテントは自分のだけだった。
テントに関してはどのメーカーが多いとか特に無いねぇ。バラバラ。
自分もどのテントを買うか迷ったけど、自分の好きなのを買えば良いんじゃないかなー。
ただモンベルの黄色いテントはどこのテン場でもいくつかはあったな。
すでにその頃にはガスが出てきて、さっきまで綺麗に見えていた風景はなし。
すぐ近くにある槍ヶ岳すら見えない。
テントの外では雨音がしていて「うわー、早くテント作らんと!」と今到着したばかりのアベックが急いで設営に取り掛かる声。早く着いてよかった。山では早寝早立ちというが、まさに、だ。
そのままテント内でゴロンと横になったらどうも眠ったみたい。
気が付けば17時前になっていた。雨音は消えてた。
テントは他の人に気兼ねなく過ごせるから良いね。
今日の小屋泊まりはキツイだろう。
今後も出来るだけテントを持って山に来よう。
そして夕食。アウトドアショップで買ったアルファ米を食べた。
アルファ米どころか、おしるこや味噌汁含めどんだけ食うねん!
って言うくらい腹いっぺー
 食べた。
食べた。別に腹が空いていた訳じゃない。
とにかく荷物(重り)を減らしたい一心だった

山スカートの女性に抜かれた悲しさに包まれながら、腹減ってもないのに無理やり食べる一人寂しい夕食でしたわ

重さの要因の一つにはこいつもある。
お気に入りのコールマンのフェザーストーブ。
前回のキャンプで使わせてもらったガスストーブの使い勝手が非常に良くて、軽量化を考えて買おうかとも考えた。でもそれだけの事に買うのも・・・。それにこいつと一緒に最初のテント泊がしたかったという気持ちもあった。
・・・今考えれば借りたら良かったな

夕暮れが楽しみだったがガスってしまい、ガスの切れ間から一瞬一瞬、時折見れるだけ。
そして何もする事も無いので、19時には早めの就寝。
明日はあの有名な大キレット越えだ。早く寝て今日の疲れを回復させないと。
(キレットは漢字で切戸と書き、山稜がV字型に深く切れこんで低くなっている場所の意味)
大キレット。
雑誌の言葉を引用すると「国内縦走路では屈指の難路」らしく、飛騨乗越をクリアした先の尾根でおばちゃんに話しかけられた「大キレットを抜けられてきたんですか?」という言葉からもその重みが分かる。
初めて行く難路と呼ばれるコース。
いったいどんな道が待ち構えているんだろうか・・・と思いながら眠りに就いた。
■登山 ジャンダルム 初日終了
その5に続く
2010年07月21日
登山 ジャンダルム その3
初日のルートMAP

■17日(初日)の続きから
黄フリース氏と別れた後、左肩の激痛に耐えながらひたすら忍耐の登山。
一歩一歩確実に近づいてはいる筈だけど風景がゆっくりしか変わらない。
でも嫌な気はしない。それほど最高の風景だった。
低山の風景にしか知らない田舎者の自分にはすべてが新鮮だ
この辺りではすでに森林限界を抜け、高い木々は無く、あるのは背の低い高山植物とひたすら石・石・石。
石の登山道を忍耐のマイペースで歩いていると、あれ?人影が・・・。
あれ?あれ、もしかしてー!
キター!
青メガネ氏だー!
見つけたー!!
槍平小屋で引き離された青メガネ氏を発見。
まだ80m程は離れてるけど、3時間もあの後姿を見て歩いたんだ。
間違いなく分かる。あれは青メガネ氏だ。
青メガネ氏はちょうど飛騨乗越から西鎌尾根へとバイパスする分岐点で休んでいる様子。
よーし!ここで一気に追いつくぞー!と俄然やる気になった瞬間、青メガネ氏がこっちを振り向いた。
3時間も後を付けられたんだからあっちもこっちを分かってる。
こっちを見つけられた瞬間、避けるようにして青メガネ氏は出発。えー!!
しかも飛騨乗越方面じゃなく、西鎌尾根に抜けるバイパスルートへ。
(なんやー、行く場所違うんかー。槍ヶ岳山荘で喋ろうと思ってたのになー )と、この時は思った。
)と、この時は思った。
後で槍ヶ岳山荘で出会う事になる。
これも後で聞いた話だが、タイムコース的には20分ほどのロスになるが、尾根に出てしまうので歩いてみると体も楽で、尾根沿いに槍ヶ岳山荘出られるとの事。20分のロスも埋められるくらいだそうだ。
今考えてみれば青メガネ氏のあの分岐点での休憩はMAPを見ながらルートを選別していたんだろう。
分岐点で何も考えなかった(そんな余裕が無かった)自分とは山の経験が違う、って感じ。
10:13 目標を再度失い飛騨乗越のルートをひたすら歩いていたら頂上の様子が見えてきた。
目を凝らすと・・・あれ?なんか建物が見える!

写真では見えにくいけど、ピークとピークの間に間違いなく建物が見える。
たぶんあれが槍ヶ岳山荘だ!ヨッシャー!
と、元気が出たのはその瞬間だけで、ゆっくりとしか風景が変わらないのは今までと同じ。
相変わらず左肩痛は激しく、すぐに元の忍耐のマイペースへ。
見えてはいるけど果てしなく遠くに感じる槍ヶ岳山荘は目標にならない。
今の目標は・・・とにかく目の前のルート目印だけ。
5m間隔ほどで付けられているその目印まで行って一休み。
その間に次の目印を探して、またその目印を次の目標に・・・そして一休み。
一体どれくらい同じ行動を繰り返したのか・・・槍ヶ岳山荘は果てしなく遠い・・・
ふと下を見れば相当遠くに黄フリース氏がいる。相変わらずの遅ペースだ。
でもその前に本日初めて見る2人組が居た。あれ?今まであんな2人いたっけな?
しばらくしてまた振り返ると2人組の姿がハッキリと分かる距離に近付いて来てた。
早っ!!
2人組の姿を見かけてから30分程は頑張って追いつかれない様に歩いた。
でも明らかにスピードが違う。
はい、白旗でーす
道を譲るついでにどっかりと腰を下ろして休憩した。
そしてじっくり2人組を観察する。
見る見る2人組が近付いて来る。
驚いた。
先頭を歩いてるのは山スカートの女性だった。
長身細身の20代後半くらいのカップル。
やや経験が少ないのか、女性をサポートするように男性が後ろから声掛けするという感じ。
正直、ショックだった。
山で女の人に抜かれるなんて思ってもみなかった。
ただその装備は随分軽装だ。
ザックも小さいしテン泊じゃなく小屋泊まりだな、と挨拶を交わしながら思った。
ただ黄フリース氏と後で話したら「あれ、(ザックに)何にも入っとらんと思うで。日帰りやろ。早過ぎるもの。」と言っていた。事実、槍ヶ岳山荘に到着後しばらくはそのカップルの姿を見たが、その後は結局一度も見なかった。帰ったんだろう。
初めて知った北アルプスの日帰りという選択肢。
色々な人が居るなー。
それに荷物が軽いっていうのは相当のアドバンテージなんだな、って重要な経験を身を持って知る。
自分の背中には18キロのザックが肩にザックリ食い込んでいるぜ

カップルに抜かれた後、また忍耐の歩きを続けている雪渓が出て来た。
標高的には2800m程か。
雪渓といっても一部分だけ残ってるという程度で、少し迂回すれば歩かずに済む。
でも迂回すれば100m。雪渓を直登すれば30mだ。疲れた体にこの差はでかい。
ほぼ徹夜に近い体で疲労はピーク。
更に初体験となる雪渓を歩きたいという気持ちが勝って直登する事に。
実はその上で先ほどの2人組カップルの女性が直登してたんだ。
でも男性はなぜか迂回。
ザックをガサゴソしてたから、今考えるとアイゼンを女性に渡していたのかもしれないな。
そんな事は知らない自分、(彼女が行けるのに俺が行けん訳ねー)と馬鹿丸出しで雪渓にアタック。
たった30mの直登。
雪国生まれと言う慢心もあった。
少し歩いただけで違和感を感じる。
なんか感触が違う。
カッチカチやで!
30mの半分を過ぎた辺りから危険を感じる。
これ、一旦滑ったら止まらんな・・・。
かろうじて頼りになるのは2本のトレッキングポール。
今もこれを頼りに4本足で歩いているけど、もしもの時には片手に持ってピッケル代わりに・・・って考えてた。(でもそれでも多分止まらんなー。雪が硬過ぎて刺さらんわ・・・)
たった30mの雪渓。
直登し終わった瞬間(もう2度と歩かねー!)と心に決めた。
急がば回れ。
今回の登山で実感した言葉だ。
登山ルートの目印。これも絶対に蔑ろにしてはいけない。
そこにあるという事は意味のある事なんだ。無い所には無い事の意味がある。
ちょっと横着して目印の無い場所を通ってヒヤッとした事がこの登山中、何度もあった。
急がば回れ。普段の日常でも使う言葉だが、命に関わる登山では肝に銘じておかなければ。。。
11:04 長く辛い忍耐の歩きもついに実を結ぶ。尾根だ。尾根が見えてきたー!
尾根に着いた矢先、槍ヶ岳方面から来た登山者と遭遇。男女女3人のパーティ。
50歳ほどの女性に声を掛けられた。
「大キレットを抜けられてきたんですか?」
「いえ、新穂からです・・・」
もう愛想笑いする元気も無い。とにかく早くザックを下ろしたい
11:15 そして、ようやく、ようやく到着。本日の最終目的地、槍ヶ岳山荘!

山荘のすぐ脇に見えるのが槍ヶ岳だ。日本で5番目(3180m)に高い山。超が付く人気の山。
そしてすでにテン場(テント場のこと)には1張りのテントが。早えー。まだ11時過ぎやで・・・。
更に今からテントを設営しようとしてる人物一人。
あれれ???
なんか見たような人物だ。
なんとよく見ると青メガネ氏!
当然喋ってはいないが、あっちもこっちも面識はある。
「あれ?いつ着かれたんですかぁ?」もう疲労困憊だ。
「10分ほど前です。西鎌尾根から尾根伝いに来たんで・・・」と青メガネ氏。
正直、その時点ではニシカマオネ?なんじゃそりゃ?状態。
基本的知識がまったく無いというのもあるし、考えれる状況でもなかった。
とにかく、とにかく、肩が痛い!!!
初めて入る山小屋。
受付のお姉ちゃんが対応してくれた。
テン泊を伝えると500円払って受付完了。
水は200円/1Lで買える事も教えてくれた。
(売るほどあります、そう言いたかった・・・ )
)
そして初めてのソロテント設営。
この日のために購入したプロモンテの山岳テント。

プロモンテ(PuroMonte) 2人用 超軽量山岳テント
ソロテントと言いながら2人用を購入。いつかいくみんとテン泊する時の事も考えて。
2人用なので当然だけど、ソロで使用するには室内は十分広い。でも1人用と比べても重さ的にはあまり変わらないので大柄な人であれば2人用をお奨めする。

プロモンテ(PuroMonte) VL23対応グランドシート
一応グランドシートも同時に購入。確かにテントのグランドはペラペラでテン場の石底ではいつ穴が空いても不思議ない。山での使用を考えると雨の事を考えるべきで、出来れば揃えておいた方が良いと思う。大きなものではないので、テントのスタッフバッグに一緒に入れて仕舞えます。
テントも張り終え、くそ重いザックをテントに置き去りにし身軽になった体で目指すは槍ヶ岳!
槍ヶ岳山荘の目と鼻の先にその切っ先がある。いざ登るべし!
コースタイムで30分。疲れた体でもサクッと登れる、はずだった・・・。
でも渋滞。槍の山頂に向かう人の波に飲まれ足止めを食らう。
そしてようやく辿り着いた槍ヶ岳の山頂。

近くのおばちゃんと写真の撮り合いっこ。
山頂は10人も人が居たらちょっと危険なのですぐに退散。
そしたら今度は下りも足止め。
60才位のおじさんの後ろに自分と同年代であろうCanonの一眼カメラを持った男性。そして自分。
で、そのおじさんが下りるのやたらめったら遅い。
別に急いで下りる理由も無いが、常識からしても遅すぎる。。。
おじさんはカメラを持った男性に「先に行く?」と声を掛けるが、「いやいや良いですー。ゆっくり行って下さい。」と返答。。。(こらこらー。先に行かせてもらいなさーい!!)と私の心は叫んだ
この時このおじさんに好青年的な返答をしたCanon一眼カメラの人物。
この人物が今回のこのジャンダルムへの挑戦登山で私の最も重要な関係者となるのはその翌日の事である。旅とはなんとも面白いものである。
その4へ続く
■17日(初日)の続きから
黄フリース氏と別れた後、左肩の激痛に耐えながらひたすら忍耐の登山。
一歩一歩確実に近づいてはいる筈だけど風景がゆっくりしか変わらない。
でも嫌な気はしない。それほど最高の風景だった。
低山の風景にしか知らない田舎者の自分にはすべてが新鮮だ

この辺りではすでに森林限界を抜け、高い木々は無く、あるのは背の低い高山植物とひたすら石・石・石。
石の登山道を忍耐のマイペースで歩いていると、あれ?人影が・・・。
あれ?あれ、もしかしてー!
キター!
青メガネ氏だー!
見つけたー!!

槍平小屋で引き離された青メガネ氏を発見。
まだ80m程は離れてるけど、3時間もあの後姿を見て歩いたんだ。
間違いなく分かる。あれは青メガネ氏だ。
青メガネ氏はちょうど飛騨乗越から西鎌尾根へとバイパスする分岐点で休んでいる様子。
よーし!ここで一気に追いつくぞー!と俄然やる気になった瞬間、青メガネ氏がこっちを振り向いた。
3時間も後を付けられたんだからあっちもこっちを分かってる。
こっちを見つけられた瞬間、避けるようにして青メガネ氏は出発。えー!!
しかも飛騨乗越方面じゃなく、西鎌尾根に抜けるバイパスルートへ。
(なんやー、行く場所違うんかー。槍ヶ岳山荘で喋ろうと思ってたのになー
 )と、この時は思った。
)と、この時は思った。後で槍ヶ岳山荘で出会う事になる。
これも後で聞いた話だが、タイムコース的には20分ほどのロスになるが、尾根に出てしまうので歩いてみると体も楽で、尾根沿いに槍ヶ岳山荘出られるとの事。20分のロスも埋められるくらいだそうだ。
今考えてみれば青メガネ氏のあの分岐点での休憩はMAPを見ながらルートを選別していたんだろう。
分岐点で何も考えなかった(そんな余裕が無かった)自分とは山の経験が違う、って感じ。
10:13 目標を再度失い飛騨乗越のルートをひたすら歩いていたら頂上の様子が見えてきた。
目を凝らすと・・・あれ?なんか建物が見える!
写真では見えにくいけど、ピークとピークの間に間違いなく建物が見える。
たぶんあれが槍ヶ岳山荘だ!ヨッシャー!

と、元気が出たのはその瞬間だけで、ゆっくりとしか風景が変わらないのは今までと同じ。
相変わらず左肩痛は激しく、すぐに元の忍耐のマイペースへ。
見えてはいるけど果てしなく遠くに感じる槍ヶ岳山荘は目標にならない。
今の目標は・・・とにかく目の前のルート目印だけ。
5m間隔ほどで付けられているその目印まで行って一休み。
その間に次の目印を探して、またその目印を次の目標に・・・そして一休み。
一体どれくらい同じ行動を繰り返したのか・・・槍ヶ岳山荘は果てしなく遠い・・・

ふと下を見れば相当遠くに黄フリース氏がいる。相変わらずの遅ペースだ。
でもその前に本日初めて見る2人組が居た。あれ?今まであんな2人いたっけな?
しばらくしてまた振り返ると2人組の姿がハッキリと分かる距離に近付いて来てた。
早っ!!
2人組の姿を見かけてから30分程は頑張って追いつかれない様に歩いた。
でも明らかにスピードが違う。
はい、白旗でーす

道を譲るついでにどっかりと腰を下ろして休憩した。
そしてじっくり2人組を観察する。
見る見る2人組が近付いて来る。
驚いた。
先頭を歩いてるのは山スカートの女性だった。
長身細身の20代後半くらいのカップル。
やや経験が少ないのか、女性をサポートするように男性が後ろから声掛けするという感じ。
正直、ショックだった。
山で女の人に抜かれるなんて思ってもみなかった。
ただその装備は随分軽装だ。
ザックも小さいしテン泊じゃなく小屋泊まりだな、と挨拶を交わしながら思った。
ただ黄フリース氏と後で話したら「あれ、(ザックに)何にも入っとらんと思うで。日帰りやろ。早過ぎるもの。」と言っていた。事実、槍ヶ岳山荘に到着後しばらくはそのカップルの姿を見たが、その後は結局一度も見なかった。帰ったんだろう。
初めて知った北アルプスの日帰りという選択肢。
色々な人が居るなー。
それに荷物が軽いっていうのは相当のアドバンテージなんだな、って重要な経験を身を持って知る。
自分の背中には18キロのザックが肩にザックリ食い込んでいるぜ


カップルに抜かれた後、また忍耐の歩きを続けている雪渓が出て来た。
標高的には2800m程か。
雪渓といっても一部分だけ残ってるという程度で、少し迂回すれば歩かずに済む。
でも迂回すれば100m。雪渓を直登すれば30mだ。疲れた体にこの差はでかい。
ほぼ徹夜に近い体で疲労はピーク。
更に初体験となる雪渓を歩きたいという気持ちが勝って直登する事に。
実はその上で先ほどの2人組カップルの女性が直登してたんだ。
でも男性はなぜか迂回。
ザックをガサゴソしてたから、今考えるとアイゼンを女性に渡していたのかもしれないな。
そんな事は知らない自分、(彼女が行けるのに俺が行けん訳ねー)と馬鹿丸出しで雪渓にアタック。
たった30mの直登。
雪国生まれと言う慢心もあった。
少し歩いただけで違和感を感じる。
なんか感触が違う。
カッチカチやで!

30mの半分を過ぎた辺りから危険を感じる。
これ、一旦滑ったら止まらんな・・・。
かろうじて頼りになるのは2本のトレッキングポール。
今もこれを頼りに4本足で歩いているけど、もしもの時には片手に持ってピッケル代わりに・・・って考えてた。(でもそれでも多分止まらんなー。雪が硬過ぎて刺さらんわ・・・)
たった30mの雪渓。
直登し終わった瞬間(もう2度と歩かねー!)と心に決めた。
急がば回れ。
今回の登山で実感した言葉だ。
登山ルートの目印。これも絶対に蔑ろにしてはいけない。
そこにあるという事は意味のある事なんだ。無い所には無い事の意味がある。
ちょっと横着して目印の無い場所を通ってヒヤッとした事がこの登山中、何度もあった。
急がば回れ。普段の日常でも使う言葉だが、命に関わる登山では肝に銘じておかなければ。。。
11:04 長く辛い忍耐の歩きもついに実を結ぶ。尾根だ。尾根が見えてきたー!
尾根に着いた矢先、槍ヶ岳方面から来た登山者と遭遇。男女女3人のパーティ。
50歳ほどの女性に声を掛けられた。
「大キレットを抜けられてきたんですか?」
「いえ、新穂からです・・・」
もう愛想笑いする元気も無い。とにかく早くザックを下ろしたい

11:15 そして、ようやく、ようやく到着。本日の最終目的地、槍ヶ岳山荘!
山荘のすぐ脇に見えるのが槍ヶ岳だ。日本で5番目(3180m)に高い山。超が付く人気の山。
そしてすでにテン場(テント場のこと)には1張りのテントが。早えー。まだ11時過ぎやで・・・。
更に今からテントを設営しようとしてる人物一人。
あれれ???
なんか見たような人物だ。
なんとよく見ると青メガネ氏!
当然喋ってはいないが、あっちもこっちも面識はある。
「あれ?いつ着かれたんですかぁ?」もう疲労困憊だ。
「10分ほど前です。西鎌尾根から尾根伝いに来たんで・・・」と青メガネ氏。
正直、その時点ではニシカマオネ?なんじゃそりゃ?状態。
基本的知識がまったく無いというのもあるし、考えれる状況でもなかった。
とにかく、とにかく、肩が痛い!!!

初めて入る山小屋。
受付のお姉ちゃんが対応してくれた。
テン泊を伝えると500円払って受付完了。
水は200円/1Lで買える事も教えてくれた。
(売るほどあります、そう言いたかった・・・
 )
)そして初めてのソロテント設営。
この日のために購入したプロモンテの山岳テント。

プロモンテ(PuroMonte) 2人用 超軽量山岳テント
ソロテントと言いながら2人用を購入。いつかいくみんとテン泊する時の事も考えて。
2人用なので当然だけど、ソロで使用するには室内は十分広い。でも1人用と比べても重さ的にはあまり変わらないので大柄な人であれば2人用をお奨めする。

プロモンテ(PuroMonte) VL23対応グランドシート
一応グランドシートも同時に購入。確かにテントのグランドはペラペラでテン場の石底ではいつ穴が空いても不思議ない。山での使用を考えると雨の事を考えるべきで、出来れば揃えておいた方が良いと思う。大きなものではないので、テントのスタッフバッグに一緒に入れて仕舞えます。
テントも張り終え、くそ重いザックをテントに置き去りにし身軽になった体で目指すは槍ヶ岳!
槍ヶ岳山荘の目と鼻の先にその切っ先がある。いざ登るべし!
コースタイムで30分。疲れた体でもサクッと登れる、はずだった・・・。
でも渋滞。槍の山頂に向かう人の波に飲まれ足止めを食らう。
そしてようやく辿り着いた槍ヶ岳の山頂。
近くのおばちゃんと写真の撮り合いっこ。
山頂は10人も人が居たらちょっと危険なのですぐに退散。
そしたら今度は下りも足止め。
60才位のおじさんの後ろに自分と同年代であろうCanonの一眼カメラを持った男性。そして自分。
で、そのおじさんが下りるのやたらめったら遅い。
別に急いで下りる理由も無いが、常識からしても遅すぎる。。。
おじさんはカメラを持った男性に「先に行く?」と声を掛けるが、「いやいや良いですー。ゆっくり行って下さい。」と返答。。。(こらこらー。先に行かせてもらいなさーい!!)と私の心は叫んだ

この時このおじさんに好青年的な返答をしたCanon一眼カメラの人物。
この人物が今回のこのジャンダルムへの挑戦登山で私の最も重要な関係者となるのはその翌日の事である。旅とはなんとも面白いものである。
その4へ続く
2010年07月20日
登山 ジャンダルム その2
初日のルートMAP

■17日(初日)
04:50 新穂高の無料駐車場の車中で1時間くらい仮眠をし、周りがざわつき始めた4時過ぎから準備を始め、ようやく出発したのが4:50。あたりはすっかり明るくなってた
う~ん、出遅れた!
いざ歩き出したものの、道が分からない
何人もザックを背負って行くけど、明らかに自分とは違うルートの人たち。
自分の行く方向はわかってるんだけど、なにぶん初めてなもんで登山道の入口が分からない。
不安になってるとただ一人だけ自分の行きたいルートへ歩き出した人が居た
中肉中背、青い服着たメガネの30代後半くらいのベテランぽい。(以下 青メガネ氏)
よし、この人に付いて行く!
一定のペースで迷い無く歩く青メガネ氏の先導で、俄然やる気がみなぎる。
この道で間違いない!
道はすでに登山道の一部を確実にトレースしていたので、もう間違えようが無い。
自分のマイペースより若干遅い青メガネ氏をそこでパスして自分のペースに切り替えた。
まず向かう先は穂高平の避難小屋。休憩する気は無いけど、まずそこが目標になる。
ほぼ一本道。この辺りの登山道はまだ山の中の車道。
05:44 黙々と歩き続けると目的地の穂高平避難小屋に着いた。
でもなんかおかしい。抜いた事あるような気がする人達が休憩してる・・・。
もちろん休憩はせずに歩き続けるが、気になってMAPの確認。
すると・・・車道をショートカットするように登山道がある
めっちゃタイムロスやー!!
くそー!俺頭ワリー と思いながら
と思いながら
ひょっとして・・・と先を急ぐと・・・いた! 青メガネ氏!
青メガネ氏!
めっちゃ恥ずかしいやんけー!
もう二度と同じ轍は踏むまい、と学習した私は青メガネ氏の後ろを付かず離れず付いていく
そして最初に見えたアルプス的な風景。

これ何の山だろう・・・とMAPを見る。たぶん笠ヶ岳だ。
06:16 計算されたように一定のペースで歩く青メガネ氏について白出沢へ。
その足取りは間違いなく上級者。まったくブレない。
自分は初めてのアルプスで歩くペースが分からない。しばらくはこの人に付いて行こう。
07:09 白出沢からさらに進み、時間的には滝谷出合くらいだろうか。
上流を見上げるとなんか見たことある風景が。

笠ヶ岳は「たぶん」だけど、これは間違いなく分かる。
ジャンダルムだ。
→北穂やし。。。
自分の立てた予定通り行けば明後日になる。
明後日、あのピークに立てるだろうか・・・。
07:40 槍平小屋のやや手前。ジャンダルムが視界から消える前に撮った写真。

奥に見える山、左から奥穂高~ジャンダルム~間ノ岳(たぶん)。
この稜線を明後日すべて踏破する・・・出来るだろうか
07:50 槍平小屋到着。
ここまで淡々と同じペースで歩き続けてきた青メガネ氏。(と自分)
もう歩き出して3時間経ってる。
ここで休憩だろうから、少し話しかけてみようかな、と考える。
というのも、どうもザックの背負い方が悪かったらしく激しく左肩が痛い。
頼むから休憩させてくれ、という感じだった
この1時間くらいは(なんでこんなに肩痛いんだー!)と思いながらの我慢の歩き。
後で分かったのだけど、ザックをしっかり密着させてなかったのが原因らしい。
槍平小屋は自分にとって初めて見る山小屋。
(へぇー、こんな場所にあるんだー)とザックを下ろす場所を探していると青メガネ氏はそのまま小屋の裏へ歩いて行く。えっ!?
まさかまさかの槍平小屋スルー
どんだけ体力あんねん。結構なペースで歩いてるでぇ
絶対無理!と半分泣きべそでザックを下ろす
残念ながらここで青メガネ氏とはお別れだ。
とにかくキツイのは肩。足腰や体力的には問題ない。ただただ左肩が痛い・・・
左肩の休憩がてら軽食を取る。大好物のスニッカーズ!
いつもはメガトン級のカロリーを誇るこのお菓子はおいそれと食べれない。
ただ今は違う!今が食べる時だー!
槍平小屋にはグラサンでタバコをぷか~と吹かしてる登山者が一人だけ休憩中だった。
細身の小柄で40代前半に見える黄色フリースを着た男性。経験は・・・判断不能。
騎手の四位洋文そっくりの人物だ
(以下 黄フリース氏)
最初に着いた時に挨拶だけ交わしたけど、20分ほど休憩してる間に行ってしまったようだ。
08:10 槍平小屋を出発。
左肩を休憩させる為だけに20分の大休憩。
奮発して大好物のスニッカーズまで投入したが、ザックを担いだ瞬間から再発する左肩痛
スニッカーズ、肩痛には効果なし!
仕方ない、今日はこのまま歩くしかない。。。
なにせザックが重い。事前軽量では軽量化を図ったものの18キロ程だった。
これも後で笑われた話だが、水を4Lも持って行ったのが間違いだった。
アルプスでは小屋がしっかりしてるから、飲み水はその都度確保(購入)出来るらしい。
小屋など無い低山登山に慣れた自分は(水はあるに越した事は無い)という意識があるから頑張って持ってきたけど、飲まないならただの重りだ。左肩痛に悩まされ、何度(捨てたろかー! )と思った事か
)と思った事か
ここから目指すルートは飛騨乗越。
(登山用語って読みにくいねー。一般ピーポーには読めん。これはのっこしと読み、二つの峰の間の低くなった部分で、尾根を乗り越えるところの意味らしい)
ここからは一気に標高を上げるのでキツイのは目に見えてる。本日の核心部だ。
槍平小屋からこのMAPのコースタイムで宿泊予定の槍ヶ岳山荘まで5時間。
青メガネ氏は居なくなったが、登山ルートはしっかりしているので一人で歩いてても迷う事は無い。
マイペースで森の中を歩く事30分程。
前に人影が見えた。槍平山荘でタバコ吹かしてた黄フリース氏だ。
その歩みは・・・驚くほど遅い
ただ後姿を見ていると道具やトレッキングポールの突き方等で経験をかなり積んでるのは分かる。
並ぶ間もなくパス。あちらも気持ち良く抜かせてくれた。やはり相当な経験者だろう。
09:27 標高を上げ森を抜けたらバーンと景色が開けた。MAPでは花マークの付いたやや手前。
もう左肩が限界だ
休憩休憩休憩・・・もう頭はザックを下ろす事しか考えてない。
ちょうど良い大きさの石があり、後方に笠ヶ岳が綺麗に見えていたのでついでに写真撮影
左肩が悲鳴を上げているので出発したくないが、歩き出さないことには始まらない。
後ろから確実に黄フリース氏が来てるのは分かってた。
黄フリース氏がここに到着するまで休もう・・・って決めた。

笠ヶ岳、さっきまで綺麗に見えていたのに。。。やや雲が出てきた。
そして黄フリース氏がやって来た。早い。あっという間の休憩だった。(写真の人物)
あの遅ペースで・・・。
山では多少ペースが早くてもなかなか差は広がらない、って実感した。
逆に自分のペースを持ってる人の強みを感じた瞬間だ。
自分も青メガネ氏や黄フリース氏のように自分のペースを確立しないと駄目だな。
あまりに休憩が短かったので黄フリース氏とスポーツドリンクを作りながらちょっとお喋り。
黄フリース氏もここで休憩を取るつもりのようだった。
内容は2週間前にも同じルートでここからもう少し先の2600m付近まで登った事。その時は雪が多く、ルート目印も見えにくい状態。そして更にそこでガスってしまい5m先が見えなくなり、どうしようか思案していたところ西鎌尾根からエスケープして来た2人組に出合い、そのパーティも槍ヶ岳を目指していたが尾根は強風でとても歩ける状態でないという情報を得て一緒に下山した事など。
話の内容からもやはり黄フリース氏は相当の経験者だった。
今日の行き先は一緒。槍ヶ岳山荘だ。
「じゃあ、また頂上で会いましょう」と言って別れ、一足先に槍ヶ岳山荘に向かった。
その3へ続く
■17日(初日)
04:50 新穂高の無料駐車場の車中で1時間くらい仮眠をし、周りがざわつき始めた4時過ぎから準備を始め、ようやく出発したのが4:50。あたりはすっかり明るくなってた

う~ん、出遅れた!

いざ歩き出したものの、道が分からない

何人もザックを背負って行くけど、明らかに自分とは違うルートの人たち。
自分の行く方向はわかってるんだけど、なにぶん初めてなもんで登山道の入口が分からない。
不安になってるとただ一人だけ自分の行きたいルートへ歩き出した人が居た

中肉中背、青い服着たメガネの30代後半くらいのベテランぽい。(以下 青メガネ氏)
よし、この人に付いて行く!

一定のペースで迷い無く歩く青メガネ氏の先導で、俄然やる気がみなぎる。
この道で間違いない!

道はすでに登山道の一部を確実にトレースしていたので、もう間違えようが無い。
自分のマイペースより若干遅い青メガネ氏をそこでパスして自分のペースに切り替えた。
まず向かう先は穂高平の避難小屋。休憩する気は無いけど、まずそこが目標になる。
ほぼ一本道。この辺りの登山道はまだ山の中の車道。
05:44 黙々と歩き続けると目的地の穂高平避難小屋に着いた。
でもなんかおかしい。抜いた事あるような気がする人達が休憩してる・・・。
もちろん休憩はせずに歩き続けるが、気になってMAPの確認。
すると・・・車道をショートカットするように登山道がある

めっちゃタイムロスやー!!

くそー!俺頭ワリー
 と思いながら
と思いながら
ひょっとして・・・と先を急ぐと・・・いた!
 青メガネ氏!
青メガネ氏!めっちゃ恥ずかしいやんけー!

もう二度と同じ轍は踏むまい、と学習した私は青メガネ氏の後ろを付かず離れず付いていく

そして最初に見えたアルプス的な風景。
これ何の山だろう・・・とMAPを見る。たぶん笠ヶ岳だ。
06:16 計算されたように一定のペースで歩く青メガネ氏について白出沢へ。
その足取りは間違いなく上級者。まったくブレない。
自分は初めてのアルプスで歩くペースが分からない。しばらくはこの人に付いて行こう。
07:09 白出沢からさらに進み、時間的には滝谷出合くらいだろうか。
上流を見上げるとなんか見たことある風景が。
笠ヶ岳は「たぶん」だけど、これは間違いなく分かる。
ジャンダルムだ。
→北穂やし。。。
自分の立てた予定通り行けば明後日になる。
明後日、あのピークに立てるだろうか・・・。
07:40 槍平小屋のやや手前。ジャンダルムが視界から消える前に撮った写真。
奥に見える山、左から奥穂高~ジャンダルム~間ノ岳(たぶん)。
この稜線を明後日すべて踏破する・・・出来るだろうか

07:50 槍平小屋到着。
ここまで淡々と同じペースで歩き続けてきた青メガネ氏。(と自分)
もう歩き出して3時間経ってる。
ここで休憩だろうから、少し話しかけてみようかな、と考える。
というのも、どうもザックの背負い方が悪かったらしく激しく左肩が痛い。
頼むから休憩させてくれ、という感じだった

この1時間くらいは(なんでこんなに肩痛いんだー!)と思いながらの我慢の歩き。
後で分かったのだけど、ザックをしっかり密着させてなかったのが原因らしい。
槍平小屋は自分にとって初めて見る山小屋。
(へぇー、こんな場所にあるんだー)とザックを下ろす場所を探していると青メガネ氏はそのまま小屋の裏へ歩いて行く。えっ!?
まさかまさかの槍平小屋スルー

どんだけ体力あんねん。結構なペースで歩いてるでぇ

絶対無理!と半分泣きべそでザックを下ろす

残念ながらここで青メガネ氏とはお別れだ。
とにかくキツイのは肩。足腰や体力的には問題ない。ただただ左肩が痛い・・・

左肩の休憩がてら軽食を取る。大好物のスニッカーズ!
いつもはメガトン級のカロリーを誇るこのお菓子はおいそれと食べれない。
ただ今は違う!今が食べる時だー!

槍平小屋にはグラサンでタバコをぷか~と吹かしてる登山者が一人だけ休憩中だった。
細身の小柄で40代前半に見える黄色フリースを着た男性。経験は・・・判断不能。
騎手の四位洋文そっくりの人物だ

(以下 黄フリース氏)
最初に着いた時に挨拶だけ交わしたけど、20分ほど休憩してる間に行ってしまったようだ。
08:10 槍平小屋を出発。
左肩を休憩させる為だけに20分の大休憩。
奮発して大好物のスニッカーズまで投入したが、ザックを担いだ瞬間から再発する左肩痛

スニッカーズ、肩痛には効果なし!

仕方ない、今日はこのまま歩くしかない。。。
なにせザックが重い。事前軽量では軽量化を図ったものの18キロ程だった。
これも後で笑われた話だが、水を4Lも持って行ったのが間違いだった。
アルプスでは小屋がしっかりしてるから、飲み水はその都度確保(購入)出来るらしい。
小屋など無い低山登山に慣れた自分は(水はあるに越した事は無い)という意識があるから頑張って持ってきたけど、飲まないならただの重りだ。左肩痛に悩まされ、何度(捨てたろかー!
 )と思った事か
)と思った事か
ここから目指すルートは飛騨乗越。
(登山用語って読みにくいねー。一般ピーポーには読めん。これはのっこしと読み、二つの峰の間の低くなった部分で、尾根を乗り越えるところの意味らしい)
ここからは一気に標高を上げるのでキツイのは目に見えてる。本日の核心部だ。
槍平小屋からこのMAPのコースタイムで宿泊予定の槍ヶ岳山荘まで5時間。
青メガネ氏は居なくなったが、登山ルートはしっかりしているので一人で歩いてても迷う事は無い。
マイペースで森の中を歩く事30分程。
前に人影が見えた。槍平山荘でタバコ吹かしてた黄フリース氏だ。
その歩みは・・・驚くほど遅い

ただ後姿を見ていると道具やトレッキングポールの突き方等で経験をかなり積んでるのは分かる。
並ぶ間もなくパス。あちらも気持ち良く抜かせてくれた。やはり相当な経験者だろう。
09:27 標高を上げ森を抜けたらバーンと景色が開けた。MAPでは花マークの付いたやや手前。
もう左肩が限界だ

休憩休憩休憩・・・もう頭はザックを下ろす事しか考えてない。
ちょうど良い大きさの石があり、後方に笠ヶ岳が綺麗に見えていたのでついでに写真撮影

左肩が悲鳴を上げているので出発したくないが、歩き出さないことには始まらない。
後ろから確実に黄フリース氏が来てるのは分かってた。
黄フリース氏がここに到着するまで休もう・・・って決めた。
笠ヶ岳、さっきまで綺麗に見えていたのに。。。やや雲が出てきた。
そして黄フリース氏がやって来た。早い。あっという間の休憩だった。(写真の人物)
あの遅ペースで・・・。
山では多少ペースが早くてもなかなか差は広がらない、って実感した。
逆に自分のペースを持ってる人の強みを感じた瞬間だ。
自分も青メガネ氏や黄フリース氏のように自分のペースを確立しないと駄目だな。
あまりに休憩が短かったので黄フリース氏とスポーツドリンクを作りながらちょっとお喋り。
黄フリース氏もここで休憩を取るつもりのようだった。
内容は2週間前にも同じルートでここからもう少し先の2600m付近まで登った事。その時は雪が多く、ルート目印も見えにくい状態。そして更にそこでガスってしまい5m先が見えなくなり、どうしようか思案していたところ西鎌尾根からエスケープして来た2人組に出合い、そのパーティも槍ヶ岳を目指していたが尾根は強風でとても歩ける状態でないという情報を得て一緒に下山した事など。
話の内容からもやはり黄フリース氏は相当の経験者だった。
今日の行き先は一緒。槍ヶ岳山荘だ。
「じゃあ、また頂上で会いましょう」と言って別れ、一足先に槍ヶ岳山荘に向かった。
その3へ続く
2010年07月20日
登山 ジャンダルム その1
登山をかじり出して9ヶ月。
何も知らない去年の10月にはこんな状況だったのが懐かしい
私には山の先輩(60才ちょい前)がいて、自分の知識の主は雑誌だけど、経験がある生の情報はその人からのみ。近くに山好きの人が居ない。
その先輩が昔 の席で教えてくれたキーワード。
の席で教えてくれたキーワード。
ジャンダルム
内心、(このおっさん、フランスのジャンヌ・ダルクと間違っとるやろ?)と真剣に思った。
先輩も 相当飲んでたからね・・・
相当飲んでたからね・・・
でもなぜか妙にその言葉に興味を持ち、話を聞くうちに心は(絶対に行く!)に変わってた。
ジャンダルムとは、ちょっと登山する人なら誰でも知ってる岩稜の名前で、そのジャンダルムへ行くコースは山の雑誌から抜粋すると「日本の一般縦走路、最難関コース」となっている。
で、去年、自分には珍しく目標を立てた。
1年以内にジャンダルムに行く!しかもテント泊で!
正直、すぐにでも行きたいところだったけど、装備も無い状態で気付けば冬。
それで目標を1年以内に定めた。
実は最近やってたきずみんinザックやダイエットもこの目標のため。
なんで?と言われると自分を試してみたいなのかな?
今の自分にどれくらい出来るのか?
国内最難関コースってどんなものなのか?
登山経験も何も無い自分がいったいどこまで出来るのか?
その為には今しかない。今しかその経験は出来ない。それがこの日記の意味やった。
だからその準備にガンガン トレーニングしたら意味が無い。今の自分じゃなくなる。
トレーニングしたら意味が無い。今の自分じゃなくなる。
ただある程度しないと死にに行くようなもんで・・・というジレンマ。
今までそれに関して何も書けなかったのは(本当に死ぬかもしれない)と考えていたからで、登山をやってる人にその話をすると呆れられるか本気にしてくれないかのどちらかで、正直にその話をするのも途中から億劫になった。
唯一の山の先輩も「バカか?行くのは勝手やけど、死ぬんなら一人で死ねよ。人に迷惑掛からんように。」って本気で言われた。
それ以来、ジャンダルムの話は先輩にしなくなった。
今年に入って夏山になる7月か8月に狙いを定め、6月に入って日程を7月17日~22日までの間で の日を狙う事に。
の日を狙う事に。
そして行く直前にコースを定めた。
■1日目
新穂高温泉無料駐車場→穂高平→白出沢出合→槍平小屋→飛騨乗越→槍ヶ岳山荘(テン泊)
■2日目
槍ヶ岳山荘→南岳→大キレット→北穂高岳→涸沢岳→穂高岳山荘(テン泊)
■3日目
穂高岳山荘→奥穂高岳→ジャンダルム→西穂高岳→西穂高山荘→ →新穂高温泉無料駐車場
→新穂高温泉無料駐車場
そして天気を確認、梅雨が明ける17日(土)~19日(月)の2泊3日とした。
■16日夜
荷物を準備し、22時前に 出発。
出発。
ETCの1000円への割引は大きい
02時過ぎに新穂高温泉へ到着するものの、登山者用の無料駐車場が見つからない。
30分ほどウロウロして違うよなぁ・・・と思いつつ入った深山荘露天風呂入口のさらに奥にその無料駐車場はあった。初めて行く人は注意して欲しい、と言うか絶対分からんだろこれ?
■17日早朝

4時過ぎくらいから人が活発に動き出す。
うおっ、もう行くの?という感じ。初めてのアルプス登山に戸惑うスタート。
急いで自分も準備を始めた。
その2へ続く
何も知らない去年の10月にはこんな状況だったのが懐かしい

私には山の先輩(60才ちょい前)がいて、自分の知識の主は雑誌だけど、経験がある生の情報はその人からのみ。近くに山好きの人が居ない。
その先輩が昔
 の席で教えてくれたキーワード。
の席で教えてくれたキーワード。ジャンダルム
内心、(このおっさん、フランスのジャンヌ・ダルクと間違っとるやろ?)と真剣に思った。
先輩も
 相当飲んでたからね・・・
相当飲んでたからね・・・
でもなぜか妙にその言葉に興味を持ち、話を聞くうちに心は(絶対に行く!)に変わってた。
ジャンダルムとは、ちょっと登山する人なら誰でも知ってる岩稜の名前で、そのジャンダルムへ行くコースは山の雑誌から抜粋すると「日本の一般縦走路、最難関コース」となっている。
で、去年、自分には珍しく目標を立てた。
1年以内にジャンダルムに行く!しかもテント泊で!
正直、すぐにでも行きたいところだったけど、装備も無い状態で気付けば冬。
それで目標を1年以内に定めた。
実は最近やってたきずみんinザックやダイエットもこの目標のため。
なんで?と言われると自分を試してみたいなのかな?
今の自分にどれくらい出来るのか?
国内最難関コースってどんなものなのか?
登山経験も何も無い自分がいったいどこまで出来るのか?
その為には今しかない。今しかその経験は出来ない。それがこの日記の意味やった。
だからその準備にガンガン
 トレーニングしたら意味が無い。今の自分じゃなくなる。
トレーニングしたら意味が無い。今の自分じゃなくなる。ただある程度しないと死にに行くようなもんで・・・というジレンマ。
今までそれに関して何も書けなかったのは(本当に死ぬかもしれない)と考えていたからで、登山をやってる人にその話をすると呆れられるか本気にしてくれないかのどちらかで、正直にその話をするのも途中から億劫になった。
唯一の山の先輩も「バカか?行くのは勝手やけど、死ぬんなら一人で死ねよ。人に迷惑掛からんように。」って本気で言われた。
それ以来、ジャンダルムの話は先輩にしなくなった。
今年に入って夏山になる7月か8月に狙いを定め、6月に入って日程を7月17日~22日までの間で
 の日を狙う事に。
の日を狙う事に。そして行く直前にコースを定めた。
■1日目
新穂高温泉無料駐車場→穂高平→白出沢出合→槍平小屋→飛騨乗越→槍ヶ岳山荘(テン泊)
■2日目
槍ヶ岳山荘→南岳→大キレット→北穂高岳→涸沢岳→穂高岳山荘(テン泊)
■3日目
穂高岳山荘→奥穂高岳→ジャンダルム→西穂高岳→西穂高山荘→
 →新穂高温泉無料駐車場
→新穂高温泉無料駐車場そして天気を確認、梅雨が明ける17日(土)~19日(月)の2泊3日とした。
■16日夜
荷物を準備し、22時前に
 出発。
出発。ETCの1000円への割引は大きい

02時過ぎに新穂高温泉へ到着するものの、登山者用の無料駐車場が見つからない。
30分ほどウロウロして違うよなぁ・・・と思いつつ入った深山荘露天風呂入口のさらに奥にその無料駐車場はあった。初めて行く人は注意して欲しい、と言うか絶対分からんだろこれ?

■17日早朝

4時過ぎくらいから人が活発に動き出す。
うおっ、もう行くの?という感じ。初めてのアルプス登山に戸惑うスタート。
急いで自分も準備を始めた。
その2へ続く