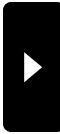2016年04月23日
甲斐駒ヶ岳~鋸(ノコギリ)岳縦走
当時持ってたiPhone4Sが死んでる時期の事で、ずいぶん書きそびれていた(もう2年近く経過・・・)が自らの記録のため残す。
2年前の9月の話です。。。
またちょっと厳しいコース(登攀1級上)に行った。
南アルプスは甲斐駒から鋸岳の縦走。(初南アルプス!)
北鎌の単独とは違い、今回は4人パーティー。山友の先輩2人と後輩1人。TUBOさんYOSIさんイッシーとしておく。
良くも悪くも色々あった山行となりました。

2年前の9月の話です。。。
またちょっと厳しいコース(登攀1級上)に行った。
南アルプスは甲斐駒から鋸岳の縦走。(初南アルプス!)
北鎌の単独とは違い、今回は4人パーティー。山友の先輩2人と後輩1人。TUBOさんYOSIさんイッシーとしておく。
良くも悪くも色々あった山行となりました。
■2014年9月13日(土)
01時半に自宅の敦賀出発。
02時に全員集合して北陸道から名神・中央道と乗り継いで伊那ICで降り、仙流荘横のバス乗り場に向かう。甲斐駒ヶ岳や仙丈ヶ岳への取付き口となる北沢峠へはバスでしかアクセス不可。ちょっと不便。タクシーくらいOKにして欲しい。
05時半に仙流荘に到着も既に長蛇の列。さすが3連休。8月が悪天候だったこともあり、みんなこの休みに照準を合わせてる様子。

臨時バスは出てるが全然追いつかず、結局1時間半バス待ちをして、北沢峠に着いたのは08時となった。
(バスの運転手さんは村の方だろうけど、車内でのトークが面白い。こういうの良いなぁ)
この日は甲斐駒ヶ岳を経由し、鋸岳への稜線上にある六合目小屋に宿泊予定である。小屋に宿泊といっても無人の避難小屋で、事前の調べによると連休ともなると10人程度しか入れないこの石室に、ひどい時には20人以上の宿泊者が来るようで、いくら一般登山道ではない難路であっても、3連休では場所確保は早い者勝ちの試練がある様子。
よって少しでも早く出発したかったが出鼻からくじかれる格好に。
(個人的には鋸よりも隠れ核心部はここだと思ってた・・・。小屋に入れるのか否か・・・))
今回はテントを持っていかないので、ここに泊まれなかった事を考えると・・・かなり不安。
ツェルト買おうと思いつつ、迷ってたら結局買いそびれた・・・
この山行の核心部である鋸岳前後は明日の予定であり、本日はサクッと甲斐駒に登り、その先にある六合目小屋まで到達する、というのが想定していた予定。
08時過ぎに北沢峠を出発。

長衛小屋のキャンプ場は朝からたくさんのテント。

最初は調子よく進んでいたが、仙水峠を過ぎてからの急登でYOSIさんの動きが悪く急ブレーキ。持病のアキレス腱が痛いらしい。
スピードをあわせてゆっくり登る。



他の2人も睡眠不足が応えているのか動きが次第に悪くなる。駒津峰過ぎの一般道と甲斐駒までの直登ルートとの分岐ではそんな体調を考慮して一般道を選択。
甲斐駒が見えてきた。


ようやく摩利支天への分岐まで来たが、イッシーがダウン。「自分はここで待ってます」と言い、イッシーを置いて摩利支天まで。こんなんで明日大丈夫か?とまたまた不安。。。
摩利支天まではデポしたザックをイッシーに見守ってもらい、空身で到達。疲れていた2人も荷物が消え、先ほどまでの動きの悪さはどこへやら。サクサクと摩利支天まで到達。軽いってすばらしい。

摩利支天

摩利支天から戻り、再びザックを背負うとやはり動きは急激に鈍る。

そしてのろのろながらようやく13:45に甲斐駒ケ岳頂上に到着。・・・遅い。



そしてみんな元気無し。。。

大丈夫なのか・・・これから一般登山道を外れて難路に踏み込むっていうのに。。。相当不安だ。。。
よって3人の状況を勘案し、いくつかの選択肢を自分が提案した。
1.鋸は断念し、このまま登ってきた道を降り、長衛小屋で宿泊。翌日下山。
2.鋸は断念し、進路を変更し、七丈第二小屋で一泊し明日ゆっくり帰る。
3.とりあえず六合目小屋まで行き、その先は明日朝の体調で決める。
個人的には2番をお奨めしたかったが、皆が出した答えは3番。。。行きたいのは分かるけど・・・だ・大丈夫・・・?
頂上でゆっくりと休憩して、鋸岳への稜線の途中にある六合目小屋に向かう事になったが、すでに鋸岳を目指そうという、つわもの達からは、相当遅れをとっているはずで、今更急いでも最下位なのは間違いない。
きっと、つわもの共が集うギューギューの小屋にこの軟弱パーティーが足を踏み入れた瞬間、挨拶も出来ないような冷たい視線にさらされる事だろう・・・
鋸岳方面・・・
大丈夫だろうか・・・


甲斐駒の頂上で休憩後、ヘルメットを装備したのち一般道を外れ、鋸岳への稜線に足を踏み入れる。さすがに難路。さっきまでワサワサいた登山者達の姿がまったくなくなる。





途中TUBOさんがザックと共に岩に挟まれ身動きが取れなくなった以外は特に何事もなく石室にたどり着く。もう16時前になっていた。

やはり自分以外の3人は疲労困憊、明日までにどこまで回復するのやら。。。
その鍵を握る体力の回復も、今回の山行で個人的にはここが核心部(苦笑)と思っていた6合目小屋の居住スペース如何にかかっている。
定員は10名。
果たしてそこに自分達パーティー4人が入り込める余地は残っているのか?
が、実は小屋を覗く以前に、もう既に小屋に入れなかったと思われるテント2張りを小屋の先に見つけてしまっており。。。
もう時間的にもビジュアル的にも絶望的である。
六合目小屋に近付くと、小屋の横で中年男3名のパーティーがオカリナの演奏中。
こんな場所でオカリナの音色はなかなか乙。
挨拶を交わすと、小屋にはすでに9名が入っているとの事。
おっ!?意外と少ないじゃん、と思ったものの9人+4人で13人は許容人員オーバー。ただ過去の記録によると14人ほどは板間で寝た実績があるらしいので、そこに期待して恐る恐る小屋内部を覗いてみる。
こんちわー
石室内で雑談していた6名の目が一斉に我々に注がれる。
パッと見、女性比率が高い。
怖い・・・
お疲れ様ーなんてあたたかい視線ではまったくなく、もう駄目よ的な刺すような視線を向け、喋ってもくれない。。。
困ってしばし沈黙していると、かろうじて聞こえる小さな声で「さすがにもう無理よねー」と会話する60代と思われる男女4人パーティーのおばさん達。暗に出て行けと言われているのをひしひしと感じる。
ただこのまま引き下がるわけにはいかない。なんせ我が隊はテント不携帯であるのですから。
ひとまず冷たい空気を打破するため、いつ登り始めたのですか?健脚ですねーなど、雑談で場を和ませて、なんとか、なんとか土間で寝ることを許される。(石室は半分が板間で就寝スペース。半分が土間、そのまま土である)
少しづつ詰めて板間に4人分をいれてくれる気はサラサラない様子。
ただこれは遅かった自分達が悪いしね。土間でも屋根があるだけマシだと思わねば・・・。
ひとまず屋根がない場所でのビバークは避けられ、最悪の事態は回避された。しかしそのまま石室内で夕食なんていう雰囲気ではなく、土間に居住スペースを確保した自分達は逃げるように外で夕食となりました。もうみんなクッタクタ。
石室のすぐ側のスペースにブルーシートを敷き宴。
パスタやおつまみ、ワインで疲れを癒しました。



いつもは単独なので、自分にとってはこういうのが一番楽しかったりするのです。
そして捨てる神あれば拾う神あり。
宴を始めて30分程した時、オカリナ3人パーティーが嬉しい言葉を掛けてくれる。
「自分達はテント持参なので、あっちでテント張りますから、板間の場所を空けます。使ってください。」
なんていい人達だ~
風景にあったオカリナのBGMを流してくれるし、場所は譲ってくれるし、素晴らしい山屋さんでした。
こんな山屋にならねばなりませんね。
宴が終わり17時過ぎに小屋に戻った時には既に先客の6人は寝袋に包まって就寝中。はやっ!
よければ一緒に宴でも、と言うつもりだったのに問答無用に態度で却下。。。

さすがにこんなに早くは寝れないので、再び外に出てワインを飲みながら風景を眺めたり、一眼レフの撮り方についてレクチャーしたりして19時前に就寝となりました。


伊那か駒ヶ根の街か、明かりが見えました。


17時前に寝てしまってる先客のパーティーは、きっと02時くらいに起きる予定なんだろうね、起こされるだろうけど、一緒に起きたらいいね、ちょっと早過ぎるけど。という事になりました。
石室とランタン

はー、板間最高。
■2014年9月14日(日)
意外と寝付けなく、朝方ようやく寝たのかな?60代男女4人パーティーの目覚ましの音に起こされる。
時計を見たら04時。
うおっ!寝過ごした!
つーか、何時間寝るつもりなの、隣のパーティー!
12時間もよー寝れるわ!!
目覚ましの音で小屋の中の全てのパーティーがバタバタと朝食の準備。
我が隊は簡単にシリアルとコーヒーの朝食でした。
05時半に行動開始。
どうもみんなの体調も最悪ではないらしく、しばらく歩いてみないと分からん、と。
「では鋸方面にとりあえず進んで、引き返すなら最終のエスケープルートとなる熊ノ穴沢まで行きましょう。
そこまでのコースタイムがコースタイム以内で行けてるのであればGO。オーバーなら体調不良と考えて、撤退という事にしましょう。」という事で賛同を得て出発。
仙丈ヶ岳が素晴らしい。

そしてモルゲンロートの時間に。
期待していなかった急遽出現したモルゲンに感動。
先ほどの仙丈ヶ岳と全然違う印象。

そしてこれから向かう鋸岳方面


中央アルプス方面

昨日と同じく最初は調子よく進む。
まず目標となるのは三ツ頭という場所で、そこまでは最初は稜線通しだが、途中からは稜線の東側の樹林帯斜面を進んでいく。ただここが厄介で、踏み跡が非常に多く道迷い数回。今回は先輩のGPSがあって(自分のGPSは死亡中・・・)何とか行けたが、危険なポイント。もし三ツ頭まで到達したとしても。三ツ頭の北側を巻くようにしてルートがあるため、そのポイントを通り過ぎてしまうと烏帽子尾根へ突き進んでしまうことは十分にありえる。注意すべきポイント。稜線の東斜面をしばらく歩くが、なるべく稜線から離れないようにしたい。

途中、北岳、仙丈ヶ岳が見事に

反対側には八ヶ岳だと思う山塊

無事に三ツ頭を通り、中ノ川乗越に到着。
ここを下って登り返す。

ここから難路が連続し始める。
エスケープするのなら一旦下った先のこのガレ場(熊ノ穴沢)を下っていく。これが最後の逃げ道。
コースタイム2時間10分のところ、2時間弱。体調不良者も出ておらず、すんなりと鋸岳決行が決まった。不安はあるが、コースタイム程で歩けてるのであれば行かねばなるまい。
中ノ川乗越からの急登を登っていく。

ここで先行していた60代男女4人パーティーに追いつく。ガラガラと落石がひどい。上に気を使いながらの登り。ただ単に前の人に付いて行くだけじゃなくて、もう少し顔振れば安定した道は見つかるのにな。。。顔振るのはサッカーも山も一緒やなーと思いながら60代4人パーティーの「ラークッ!」の声を何度も聞いていた。
08時前に第2高点と呼ばれるピークに到達。良い天気だけど、やや雲が東方面に出てきて、富士山は見れなかった。

ハーネスの紐を引き締め、降下を開始。鹿ノ窓と呼ばれる有名なポイントまでにはやや高度を落としていく。核心部がここから連続する。

そして魔の時間。
これから核心部だという、降下の途中にYOSIさんの「あっ!」と言う声で前を向くと、YOSIさんが斜面をすべり転がり落ちて行くのが見えた。
オレンジ色のヘルメットがグルングルンと回っていった。
湿っていた土道で足を滑らせたらしい。
運よく木にぶつかり止まったが、約8mの滑落。木が無かったら何十m落ちたことか。本当に運がよかった。
こちらの呼びかけに応えた時にはホッとした。大丈夫、死んでない。
動けるか?の声には腰を強打したらしく、分からない、とりあえずしばらく待ってくれ。と、しばらくその場で呻いていた。
YOSIさんの体が落ち着くまでの10分程の間、救助ヘリコプターの手配や会社への連絡、背負って下山できるかルートのシュミレーションなどを相談していたが、どうやら動けそうだという声で、今度はどうやって撤退するかの相談になる。
とりあえず狭い登山道で他の方の邪魔にもなるので、そこから10mほど下ったガラ場にゆっくりと移動するが、とっても痛そうで苦痛に顔をしかめながらYOSIさんが歩く。歩けて本当によかった。
撤退の相談をするも、核心部の直前まで来ているので、帰るとしたら今登ってきた急登を下って熊ノ穴沢のガラ場を下るか、このまま核心部に進み、予定通りの角兵衛沢のガラ場を下るかのどちらか。
中途半端な場所での滑落で、どちらにしても今のYOSIさんの状態ではキツイ。
YOSIさんに状況を伝えてみると、悩んだ末に「どっちにしてもキツイんなら、このまま鋸の方に進もう」と言う。核心部が今から連続しますよ?と聞いても、いや、その為に来たんやろ?と。いやいや、それは体が健全な状態での話でしょ?と少し冗談も言い合えるようになってきたこともあり、みんなの総意として先に進むことに決定した。
とにかく、本当に歩けてよかった。
単独ではない怖さがここにあると思う。パーティー組むとある意味、危険度が人数分増える。
良し悪しはどちらにもあるが、パーティー登山のマイナス面を実体験した出来事。
鹿ノ窓への取付き下部にあるガラ場でYOSIさんの腰休め休憩。

これからYOSIさんの荷物を持つため、大事に持っていた半分残ったワインを泣く泣く捨てる。
たった500gだけど、自分にとってもこれから核心部。
YOSIさんの荷物を持つ分、少しでも軽量化を計らねば。
そんな事を知らないYOSIさん、腰休めの場所をズラす際に「うおっ!これしょんべんちゃうんけ!」とワインを流した跡を見て騒ぐ。
・・・元気やん。
2パーティーほどをそのガラ場でやり過ごした後、YOSIさんの荷物を他の3人で分担して担ぎスタート。
鹿ノ窓までの急登というか、脆い岩場を登っていく。見上げれば小さくポカンと鹿ノ窓。

なんでこんな穴が出来たのか、不思議。その穴の中を通っていくので、その穴を目標に高度を上げていく。
脆い岩場に、自分の上には自らのパーティーを含めて6人が居り、パラパラパラパラ小石が落ちてくる。足元に気を付けながらも上部の落石コースに入らないように気を付けながら進む。
長い鎖が設置してあるが、掴んで登ると盛大に下部に石が落ちていく。掴まずに登ることは可能なので、下部に登山者が居るのであれば、出来れば鎖は掴まずに登りたいところ。


そして鹿ノ窓に到着。

意外と大きな穴。

鹿ノ窓を潜り抜けると、そこには自分達が通り過ぎるのを長く待っていてくれたカップルのパーティーが待機中。結構な時間待ってくれている筈で、まだ鹿ノ窓の下部には2人ほど登って来ていたため、少々談話。
カップルパーティーの時間潰しになればと話し出したが、鋸には何度も来ているベテランさんらしく、たくさんの情報を仕入れることが出来た。
ここで仕入れた情報でとても役立ったのが、角兵衛沢を下りた後のルートについて。
自分達のパーティーは16時の最終バスに間に合うかどうかが非常に不安なんですよねぇーなんて話してると、なんと角兵衛沢を下りたら歌宿のバス停に向かって直登するルートがある筈だという。
そんな道あるんすかっ!?
自分達の想定していた下山ルートでは角兵衛沢から川に沿って遡上し、北沢北沢峠側に登り返すルートで、時間的にギリギリ。しかも怪我人が出た今となってはコースタイム通り歩ける可能性はかなり低く、この情報は魅力的だった。御礼を言ってベテランさんと別れた。
もちろん角兵衛沢から歌宿までの直登ルートは登山道ではなく、地図にルートは記されていない。それでも自分は皆を説得させる気持ちが既に固まっていた。
鹿ノ窓付近で、歌宿と思われる場所が見えるので、写真を撮っておく。

後でそこに向かって直登だ。
谷と谷に囲まれた間を南に登って行けばまず間違いなく歌宿付近に着くはず。
地形と地図をよく照らし合わせれば等高線通りになってる事を確認しておいた。
鹿ノ窓の次には小ギャップという難所が控える。一旦崖を降下し、岩壁を登り返さないといけない。
小さく人が写ってるのが見える。


運動音痴や運動不足者には、なかなか厳しい岩壁である。
鎖に頼り過ぎるとバランスを崩しかねない。登りながらも冷静に的確な判断を。

小ギャップをクリアしてしまえば鋸岳はすぐそこである。

09:35に鋸岳到達。

YOSIさんは顔を歪めながら、六合目小屋を出発してから4時間ほどで何とか到達することが出来た。
おめ。

後は物凄いガラ場だという、角兵衛沢を下り、歌宿のバス停まで登り返すだけ。

だが登り返すのがキツイのだが。
角兵衛沢を下りはじめると、聞きしに勝るガレ場。

一歩歩けばガラガラガラガラーと足元が崩れ、下にいる人が気になって仕方ない。同じラインでは歩けない。
こんな道を3時間も歩くのーと、気を抜いた途端、転びそうになり、カメラを石にぶつけ、トレッキングポールがやや曲がる。
ああ、我が愛用のCanon EOS6Dが・・・。愛用のLEKIのポールが・・・
ま、これも味であり、歴史だと思い直し、ガラ場を歩き続ける。

そのうち、緑色のコケが付いた岩がある一帯に足を踏み入れ、その岩の上は安定度がやや高いことを後方の3人に伝えつつ下る。岩が長く動いていない箇所もあるんだな。
そんな感じでひたすら足場を確認しながら1時間少々か。

ようやく樹林帯に入る。足場が安定しておりホッとする。
ガレ場から樹林帯に変化する付近に岩小屋と呼ばれるポイントがあるはずだったが、まったく案内板もなく気付かず通過。
後から調べると本当に岩壁の下のくぼ地がそうだったらしく、ビバークポイントとして利用するような所らしい。
樹林帯をひたすら下って12:55に川原に到着。とりあえず鋸岳から角兵衛沢登り口まで下山完了。

しばし休憩するも、自分以外の3人の心が折れかけてる。
この川原でビバークでも・・・と言う言葉も出るほどに疲労困憊。。。ツェルトも持ってないのに。
この先大丈夫かなぁ。。。と思うと共に、この状態ではまずもって北沢峠までの遡上は無理と判断。何とかして歌宿まで直登する方向に皆の心を持っていかねば、と歌宿直登ルートを探し出す自分。
この辺じゃないかと思う場所をうろうろ探索。
なかなか探し出せず、3人の気持ちがやっぱり直登やめよう・・・と傾きかけたとき、とうとう見つけた!
これ、どう見ても誰かが通ったような跡じゃない???と、3人に踏み跡を見せ、直登で行きましょう!と半ば強引に決定した。
正直、獣道じゃないのかな~と自分自身思っていたが、何とかここは早く直登させないと3人の気持ちが折れる、と思ったので少々強引に決めた。
どうせ南に向かって登ってったら着くんだから、たぶん。。。
そして直登してすぐに道は不明瞭になり、消えた。
でもそんな事お構いなしに自分は先頭に立ち進む。3人の歩みはとんでもなく遅いが、余計なことを考えさせ不安がらせないように、少しでも良い道を探し選択し歩く。
完全に登山道ではない。

左手の枯れ沢に沿って歩いていく。たぶん鹿ノ窓から見えた片方の谷だ。右手側にも同じような枯れ沢があるはずで、その間をまっすぐ直登すれば歌宿に出る!と自分を信じて歩く。
1時間半ほど歩いた時に、シャトルバスのエンジン音が薄っすらと聞こえた時には嬉しかった。これで3人に元気が戻るぞと。
14:45、直登を開始して2時間弱。ひょっこりと道路が現れた時に、2日間に渡る我らの登山が終了した。歌宿のバス停から東に20mほどの場所だった。
3人の「終わったー」という声が印象的だった。



こんなところ登ってたんだもんなー


H26.9.13
02:00 敦賀発
05:20 仙流荘着
07:00 シャトルハ゛ス乗車
07:55 北沢峠下車
08:05 北沢峠出発
09:23 仙水峠
10:55 駒津峰
12:55 摩利支天
13:45 甲斐駒ケ岳頂上
15:30 岩小屋着
18:30 就寝
H26.9.14
04:00 起床、朝食
05:30 岩小屋出発
07:50 第2高点
魔の時間
09:35 鋸岳頂上
10:10 角兵衛沢のコル
12:55 角兵衛沢案内板(川原)
14:45 歌宿
15:20 シャトルハ゛ス乗車
15:55 仙流荘下車
温泉、夕食
22:30 敦賀着
山行を終えて
この山行はこれまでの自分の登山歴の中でも、良い意味でも悪い意味でもトップクラスの山行となった。
特に歌宿までの直登ルート選択は自らの登山スキルを格段にアップさせてくれたと実感。
2年近く経った今でも、このメンバーに逢えば必ずこの話題が出てくる。
それくらい皆にとっても印象深い(キツイ)山行だったんだと思う。
これ以降、光栄にも「お前は鬼や!」と呼ばれるようになった山行です。。。(苦笑)
01時半に自宅の敦賀出発。
02時に全員集合して北陸道から名神・中央道と乗り継いで伊那ICで降り、仙流荘横のバス乗り場に向かう。甲斐駒ヶ岳や仙丈ヶ岳への取付き口となる北沢峠へはバスでしかアクセス不可。ちょっと不便。タクシーくらいOKにして欲しい。
05時半に仙流荘に到着も既に長蛇の列。さすが3連休。8月が悪天候だったこともあり、みんなこの休みに照準を合わせてる様子。
臨時バスは出てるが全然追いつかず、結局1時間半バス待ちをして、北沢峠に着いたのは08時となった。
(バスの運転手さんは村の方だろうけど、車内でのトークが面白い。こういうの良いなぁ)
この日は甲斐駒ヶ岳を経由し、鋸岳への稜線上にある六合目小屋に宿泊予定である。小屋に宿泊といっても無人の避難小屋で、事前の調べによると連休ともなると10人程度しか入れないこの石室に、ひどい時には20人以上の宿泊者が来るようで、いくら一般登山道ではない難路であっても、3連休では場所確保は早い者勝ちの試練がある様子。
よって少しでも早く出発したかったが出鼻からくじかれる格好に。
(個人的には鋸よりも隠れ核心部はここだと思ってた・・・。小屋に入れるのか否か・・・))
今回はテントを持っていかないので、ここに泊まれなかった事を考えると・・・かなり不安。
ツェルト買おうと思いつつ、迷ってたら結局買いそびれた・・・
この山行の核心部である鋸岳前後は明日の予定であり、本日はサクッと甲斐駒に登り、その先にある六合目小屋まで到達する、というのが想定していた予定。
08時過ぎに北沢峠を出発。
長衛小屋のキャンプ場は朝からたくさんのテント。
最初は調子よく進んでいたが、仙水峠を過ぎてからの急登でYOSIさんの動きが悪く急ブレーキ。持病のアキレス腱が痛いらしい。
スピードをあわせてゆっくり登る。
他の2人も睡眠不足が応えているのか動きが次第に悪くなる。駒津峰過ぎの一般道と甲斐駒までの直登ルートとの分岐ではそんな体調を考慮して一般道を選択。
甲斐駒が見えてきた。

ようやく摩利支天への分岐まで来たが、イッシーがダウン。「自分はここで待ってます」と言い、イッシーを置いて摩利支天まで。こんなんで明日大丈夫か?とまたまた不安。。。
摩利支天まではデポしたザックをイッシーに見守ってもらい、空身で到達。疲れていた2人も荷物が消え、先ほどまでの動きの悪さはどこへやら。サクサクと摩利支天まで到達。軽いってすばらしい。

摩利支天

摩利支天から戻り、再びザックを背負うとやはり動きは急激に鈍る。
そしてのろのろながらようやく13:45に甲斐駒ケ岳頂上に到着。・・・遅い。
そしてみんな元気無し。。。
大丈夫なのか・・・これから一般登山道を外れて難路に踏み込むっていうのに。。。相当不安だ。。。
よって3人の状況を勘案し、いくつかの選択肢を自分が提案した。
1.鋸は断念し、このまま登ってきた道を降り、長衛小屋で宿泊。翌日下山。
2.鋸は断念し、進路を変更し、七丈第二小屋で一泊し明日ゆっくり帰る。
3.とりあえず六合目小屋まで行き、その先は明日朝の体調で決める。
個人的には2番をお奨めしたかったが、皆が出した答えは3番。。。行きたいのは分かるけど・・・だ・大丈夫・・・?
頂上でゆっくりと休憩して、鋸岳への稜線の途中にある六合目小屋に向かう事になったが、すでに鋸岳を目指そうという、つわもの達からは、相当遅れをとっているはずで、今更急いでも最下位なのは間違いない。
きっと、つわもの共が集うギューギューの小屋にこの軟弱パーティーが足を踏み入れた瞬間、挨拶も出来ないような冷たい視線にさらされる事だろう・・・
鋸岳方面・・・
大丈夫だろうか・・・
甲斐駒の頂上で休憩後、ヘルメットを装備したのち一般道を外れ、鋸岳への稜線に足を踏み入れる。さすがに難路。さっきまでワサワサいた登山者達の姿がまったくなくなる。




途中TUBOさんがザックと共に岩に挟まれ身動きが取れなくなった以外は特に何事もなく石室にたどり着く。もう16時前になっていた。

やはり自分以外の3人は疲労困憊、明日までにどこまで回復するのやら。。。
その鍵を握る体力の回復も、今回の山行で個人的にはここが核心部(苦笑)と思っていた6合目小屋の居住スペース如何にかかっている。
定員は10名。
果たしてそこに自分達パーティー4人が入り込める余地は残っているのか?
が、実は小屋を覗く以前に、もう既に小屋に入れなかったと思われるテント2張りを小屋の先に見つけてしまっており。。。
もう時間的にもビジュアル的にも絶望的である。
六合目小屋に近付くと、小屋の横で中年男3名のパーティーがオカリナの演奏中。
こんな場所でオカリナの音色はなかなか乙。
挨拶を交わすと、小屋にはすでに9名が入っているとの事。
おっ!?意外と少ないじゃん、と思ったものの9人+4人で13人は許容人員オーバー。ただ過去の記録によると14人ほどは板間で寝た実績があるらしいので、そこに期待して恐る恐る小屋内部を覗いてみる。
こんちわー
石室内で雑談していた6名の目が一斉に我々に注がれる。
パッと見、女性比率が高い。
怖い・・・
お疲れ様ーなんてあたたかい視線ではまったくなく、もう駄目よ的な刺すような視線を向け、喋ってもくれない。。。
困ってしばし沈黙していると、かろうじて聞こえる小さな声で「さすがにもう無理よねー」と会話する60代と思われる男女4人パーティーのおばさん達。暗に出て行けと言われているのをひしひしと感じる。
ただこのまま引き下がるわけにはいかない。なんせ我が隊はテント不携帯であるのですから。
ひとまず冷たい空気を打破するため、いつ登り始めたのですか?健脚ですねーなど、雑談で場を和ませて、なんとか、なんとか土間で寝ることを許される。(石室は半分が板間で就寝スペース。半分が土間、そのまま土である)
少しづつ詰めて板間に4人分をいれてくれる気はサラサラない様子。
ただこれは遅かった自分達が悪いしね。土間でも屋根があるだけマシだと思わねば・・・。
ひとまず屋根がない場所でのビバークは避けられ、最悪の事態は回避された。しかしそのまま石室内で夕食なんていう雰囲気ではなく、土間に居住スペースを確保した自分達は逃げるように外で夕食となりました。もうみんなクッタクタ。
石室のすぐ側のスペースにブルーシートを敷き宴。
パスタやおつまみ、ワインで疲れを癒しました。



いつもは単独なので、自分にとってはこういうのが一番楽しかったりするのです。
そして捨てる神あれば拾う神あり。
宴を始めて30分程した時、オカリナ3人パーティーが嬉しい言葉を掛けてくれる。
「自分達はテント持参なので、あっちでテント張りますから、板間の場所を空けます。使ってください。」
なんていい人達だ~
風景にあったオカリナのBGMを流してくれるし、場所は譲ってくれるし、素晴らしい山屋さんでした。
こんな山屋にならねばなりませんね。
宴が終わり17時過ぎに小屋に戻った時には既に先客の6人は寝袋に包まって就寝中。はやっ!
よければ一緒に宴でも、と言うつもりだったのに問答無用に態度で却下。。。

さすがにこんなに早くは寝れないので、再び外に出てワインを飲みながら風景を眺めたり、一眼レフの撮り方についてレクチャーしたりして19時前に就寝となりました。
伊那か駒ヶ根の街か、明かりが見えました。
17時前に寝てしまってる先客のパーティーは、きっと02時くらいに起きる予定なんだろうね、起こされるだろうけど、一緒に起きたらいいね、ちょっと早過ぎるけど。という事になりました。
石室とランタン
はー、板間最高。
■2014年9月14日(日)
意外と寝付けなく、朝方ようやく寝たのかな?60代男女4人パーティーの目覚ましの音に起こされる。
時計を見たら04時。
うおっ!寝過ごした!
つーか、何時間寝るつもりなの、隣のパーティー!
12時間もよー寝れるわ!!
目覚ましの音で小屋の中の全てのパーティーがバタバタと朝食の準備。
我が隊は簡単にシリアルとコーヒーの朝食でした。
05時半に行動開始。
どうもみんなの体調も最悪ではないらしく、しばらく歩いてみないと分からん、と。
「では鋸方面にとりあえず進んで、引き返すなら最終のエスケープルートとなる熊ノ穴沢まで行きましょう。
そこまでのコースタイムがコースタイム以内で行けてるのであればGO。オーバーなら体調不良と考えて、撤退という事にしましょう。」という事で賛同を得て出発。
仙丈ヶ岳が素晴らしい。
そしてモルゲンロートの時間に。
期待していなかった急遽出現したモルゲンに感動。
先ほどの仙丈ヶ岳と全然違う印象。
そしてこれから向かう鋸岳方面
中央アルプス方面
昨日と同じく最初は調子よく進む。
まず目標となるのは三ツ頭という場所で、そこまでは最初は稜線通しだが、途中からは稜線の東側の樹林帯斜面を進んでいく。ただここが厄介で、踏み跡が非常に多く道迷い数回。今回は先輩のGPSがあって(自分のGPSは死亡中・・・)何とか行けたが、危険なポイント。もし三ツ頭まで到達したとしても。三ツ頭の北側を巻くようにしてルートがあるため、そのポイントを通り過ぎてしまうと烏帽子尾根へ突き進んでしまうことは十分にありえる。注意すべきポイント。稜線の東斜面をしばらく歩くが、なるべく稜線から離れないようにしたい。
途中、北岳、仙丈ヶ岳が見事に
反対側には八ヶ岳だと思う山塊
無事に三ツ頭を通り、中ノ川乗越に到着。
ここを下って登り返す。
ここから難路が連続し始める。
エスケープするのなら一旦下った先のこのガレ場(熊ノ穴沢)を下っていく。これが最後の逃げ道。
コースタイム2時間10分のところ、2時間弱。体調不良者も出ておらず、すんなりと鋸岳決行が決まった。不安はあるが、コースタイム程で歩けてるのであれば行かねばなるまい。
中ノ川乗越からの急登を登っていく。
ここで先行していた60代男女4人パーティーに追いつく。ガラガラと落石がひどい。上に気を使いながらの登り。ただ単に前の人に付いて行くだけじゃなくて、もう少し顔振れば安定した道は見つかるのにな。。。顔振るのはサッカーも山も一緒やなーと思いながら60代4人パーティーの「ラークッ!」の声を何度も聞いていた。
08時前に第2高点と呼ばれるピークに到達。良い天気だけど、やや雲が東方面に出てきて、富士山は見れなかった。
ハーネスの紐を引き締め、降下を開始。鹿ノ窓と呼ばれる有名なポイントまでにはやや高度を落としていく。核心部がここから連続する。
そして魔の時間。
これから核心部だという、降下の途中にYOSIさんの「あっ!」と言う声で前を向くと、YOSIさんが斜面をすべり転がり落ちて行くのが見えた。
オレンジ色のヘルメットがグルングルンと回っていった。
湿っていた土道で足を滑らせたらしい。
運よく木にぶつかり止まったが、約8mの滑落。木が無かったら何十m落ちたことか。本当に運がよかった。
こちらの呼びかけに応えた時にはホッとした。大丈夫、死んでない。
動けるか?の声には腰を強打したらしく、分からない、とりあえずしばらく待ってくれ。と、しばらくその場で呻いていた。
YOSIさんの体が落ち着くまでの10分程の間、救助ヘリコプターの手配や会社への連絡、背負って下山できるかルートのシュミレーションなどを相談していたが、どうやら動けそうだという声で、今度はどうやって撤退するかの相談になる。
とりあえず狭い登山道で他の方の邪魔にもなるので、そこから10mほど下ったガラ場にゆっくりと移動するが、とっても痛そうで苦痛に顔をしかめながらYOSIさんが歩く。歩けて本当によかった。
撤退の相談をするも、核心部の直前まで来ているので、帰るとしたら今登ってきた急登を下って熊ノ穴沢のガラ場を下るか、このまま核心部に進み、予定通りの角兵衛沢のガラ場を下るかのどちらか。
中途半端な場所での滑落で、どちらにしても今のYOSIさんの状態ではキツイ。
YOSIさんに状況を伝えてみると、悩んだ末に「どっちにしてもキツイんなら、このまま鋸の方に進もう」と言う。核心部が今から連続しますよ?と聞いても、いや、その為に来たんやろ?と。いやいや、それは体が健全な状態での話でしょ?と少し冗談も言い合えるようになってきたこともあり、みんなの総意として先に進むことに決定した。
とにかく、本当に歩けてよかった。
単独ではない怖さがここにあると思う。パーティー組むとある意味、危険度が人数分増える。
良し悪しはどちらにもあるが、パーティー登山のマイナス面を実体験した出来事。
鹿ノ窓への取付き下部にあるガラ場でYOSIさんの腰休め休憩。
これからYOSIさんの荷物を持つため、大事に持っていた半分残ったワインを泣く泣く捨てる。
たった500gだけど、自分にとってもこれから核心部。
YOSIさんの荷物を持つ分、少しでも軽量化を計らねば。
そんな事を知らないYOSIさん、腰休めの場所をズラす際に「うおっ!これしょんべんちゃうんけ!」とワインを流した跡を見て騒ぐ。
・・・元気やん。
2パーティーほどをそのガラ場でやり過ごした後、YOSIさんの荷物を他の3人で分担して担ぎスタート。
鹿ノ窓までの急登というか、脆い岩場を登っていく。見上げれば小さくポカンと鹿ノ窓。
なんでこんな穴が出来たのか、不思議。その穴の中を通っていくので、その穴を目標に高度を上げていく。
脆い岩場に、自分の上には自らのパーティーを含めて6人が居り、パラパラパラパラ小石が落ちてくる。足元に気を付けながらも上部の落石コースに入らないように気を付けながら進む。
長い鎖が設置してあるが、掴んで登ると盛大に下部に石が落ちていく。掴まずに登ることは可能なので、下部に登山者が居るのであれば、出来れば鎖は掴まずに登りたいところ。
そして鹿ノ窓に到着。
意外と大きな穴。
鹿ノ窓を潜り抜けると、そこには自分達が通り過ぎるのを長く待っていてくれたカップルのパーティーが待機中。結構な時間待ってくれている筈で、まだ鹿ノ窓の下部には2人ほど登って来ていたため、少々談話。
カップルパーティーの時間潰しになればと話し出したが、鋸には何度も来ているベテランさんらしく、たくさんの情報を仕入れることが出来た。
ここで仕入れた情報でとても役立ったのが、角兵衛沢を下りた後のルートについて。
自分達のパーティーは16時の最終バスに間に合うかどうかが非常に不安なんですよねぇーなんて話してると、なんと角兵衛沢を下りたら歌宿のバス停に向かって直登するルートがある筈だという。
そんな道あるんすかっ!?
自分達の想定していた下山ルートでは角兵衛沢から川に沿って遡上し、北沢北沢峠側に登り返すルートで、時間的にギリギリ。しかも怪我人が出た今となってはコースタイム通り歩ける可能性はかなり低く、この情報は魅力的だった。御礼を言ってベテランさんと別れた。
もちろん角兵衛沢から歌宿までの直登ルートは登山道ではなく、地図にルートは記されていない。それでも自分は皆を説得させる気持ちが既に固まっていた。
鹿ノ窓付近で、歌宿と思われる場所が見えるので、写真を撮っておく。
後でそこに向かって直登だ。
谷と谷に囲まれた間を南に登って行けばまず間違いなく歌宿付近に着くはず。
地形と地図をよく照らし合わせれば等高線通りになってる事を確認しておいた。
鹿ノ窓の次には小ギャップという難所が控える。一旦崖を降下し、岩壁を登り返さないといけない。
小さく人が写ってるのが見える。

運動音痴や運動不足者には、なかなか厳しい岩壁である。
鎖に頼り過ぎるとバランスを崩しかねない。登りながらも冷静に的確な判断を。
小ギャップをクリアしてしまえば鋸岳はすぐそこである。
09:35に鋸岳到達。
YOSIさんは顔を歪めながら、六合目小屋を出発してから4時間ほどで何とか到達することが出来た。
おめ。
後は物凄いガラ場だという、角兵衛沢を下り、歌宿のバス停まで登り返すだけ。
だが登り返すのがキツイのだが。
角兵衛沢を下りはじめると、聞きしに勝るガレ場。
一歩歩けばガラガラガラガラーと足元が崩れ、下にいる人が気になって仕方ない。同じラインでは歩けない。
こんな道を3時間も歩くのーと、気を抜いた途端、転びそうになり、カメラを石にぶつけ、トレッキングポールがやや曲がる。
ああ、我が愛用のCanon EOS6Dが・・・。愛用のLEKIのポールが・・・
ま、これも味であり、歴史だと思い直し、ガラ場を歩き続ける。
そのうち、緑色のコケが付いた岩がある一帯に足を踏み入れ、その岩の上は安定度がやや高いことを後方の3人に伝えつつ下る。岩が長く動いていない箇所もあるんだな。
そんな感じでひたすら足場を確認しながら1時間少々か。
ようやく樹林帯に入る。足場が安定しておりホッとする。
ガレ場から樹林帯に変化する付近に岩小屋と呼ばれるポイントがあるはずだったが、まったく案内板もなく気付かず通過。
後から調べると本当に岩壁の下のくぼ地がそうだったらしく、ビバークポイントとして利用するような所らしい。
樹林帯をひたすら下って12:55に川原に到着。とりあえず鋸岳から角兵衛沢登り口まで下山完了。
しばし休憩するも、自分以外の3人の心が折れかけてる。
この川原でビバークでも・・・と言う言葉も出るほどに疲労困憊。。。ツェルトも持ってないのに。
この先大丈夫かなぁ。。。と思うと共に、この状態ではまずもって北沢峠までの遡上は無理と判断。何とかして歌宿まで直登する方向に皆の心を持っていかねば、と歌宿直登ルートを探し出す自分。
この辺じゃないかと思う場所をうろうろ探索。
なかなか探し出せず、3人の気持ちがやっぱり直登やめよう・・・と傾きかけたとき、とうとう見つけた!
これ、どう見ても誰かが通ったような跡じゃない???と、3人に踏み跡を見せ、直登で行きましょう!と半ば強引に決定した。
正直、獣道じゃないのかな~と自分自身思っていたが、何とかここは早く直登させないと3人の気持ちが折れる、と思ったので少々強引に決めた。
どうせ南に向かって登ってったら着くんだから、たぶん。。。
そして直登してすぐに道は不明瞭になり、消えた。
でもそんな事お構いなしに自分は先頭に立ち進む。3人の歩みはとんでもなく遅いが、余計なことを考えさせ不安がらせないように、少しでも良い道を探し選択し歩く。
完全に登山道ではない。
左手の枯れ沢に沿って歩いていく。たぶん鹿ノ窓から見えた片方の谷だ。右手側にも同じような枯れ沢があるはずで、その間をまっすぐ直登すれば歌宿に出る!と自分を信じて歩く。
1時間半ほど歩いた時に、シャトルバスのエンジン音が薄っすらと聞こえた時には嬉しかった。これで3人に元気が戻るぞと。
14:45、直登を開始して2時間弱。ひょっこりと道路が現れた時に、2日間に渡る我らの登山が終了した。歌宿のバス停から東に20mほどの場所だった。
3人の「終わったー」という声が印象的だった。
こんなところ登ってたんだもんなー

H26.9.13
02:00 敦賀発
05:20 仙流荘着
07:00 シャトルハ゛ス乗車
07:55 北沢峠下車
08:05 北沢峠出発
09:23 仙水峠
10:55 駒津峰
12:55 摩利支天
13:45 甲斐駒ケ岳頂上
15:30 岩小屋着
18:30 就寝
H26.9.14
04:00 起床、朝食
05:30 岩小屋出発
07:50 第2高点
魔の時間
09:35 鋸岳頂上
10:10 角兵衛沢のコル
12:55 角兵衛沢案内板(川原)
14:45 歌宿
15:20 シャトルハ゛ス乗車
15:55 仙流荘下車
温泉、夕食
22:30 敦賀着
山行を終えて
この山行はこれまでの自分の登山歴の中でも、良い意味でも悪い意味でもトップクラスの山行となった。
特に歌宿までの直登ルート選択は自らの登山スキルを格段にアップさせてくれたと実感。
2年近く経った今でも、このメンバーに逢えば必ずこの話題が出てくる。
それくらい皆にとっても印象深い(キツイ)山行だったんだと思う。
これ以降、光栄にも「お前は鬼や!」と呼ばれるようになった山行です。。。(苦笑)